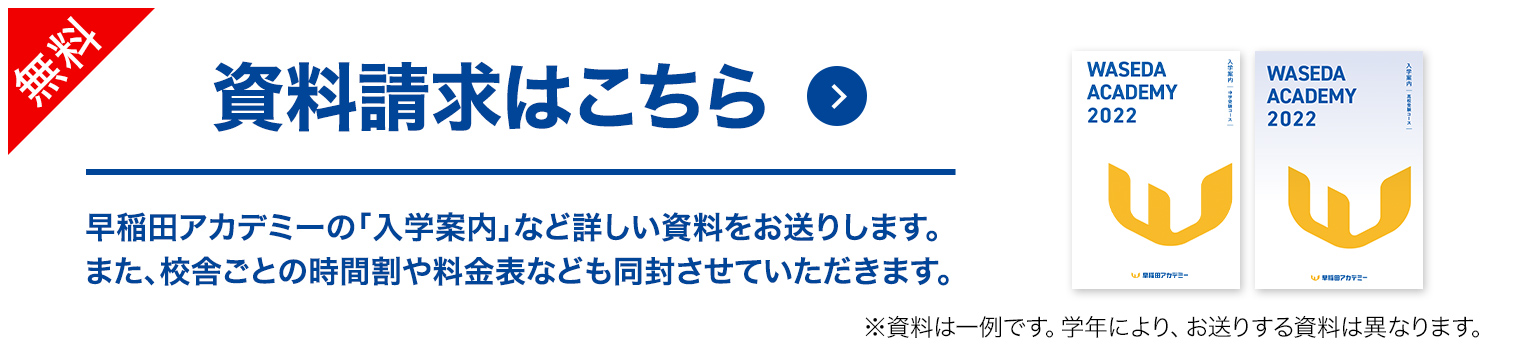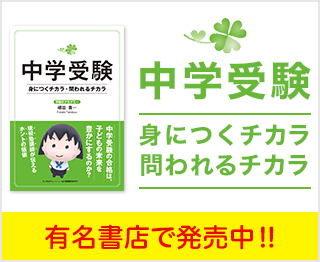『次の新たなステージへ!』
2026.02.13
2月1日から始まった東京都・神奈川県の中学入試ですが、ほぼすべての学校で入試・合格発表が終了しました。それぞれの進学先を決め、入学手続きが終わり、制服の採寸などの準備を進めていらっしゃるころかと思います。
大学受験や高校受験と違い、中学受験は「実力通りの結果」にならないことが多くあります。やはりまだ小学生ということもあり、その日の体調や精神的な状態が結果に影響するのが要因の一つです。培ってきた実力以上の力を発揮することはできませんが、当日の状態によっては実力を発揮しきれないということも出てきます。特に精神的な部分の影響は大きいものです。「緊張して問題文が頭の中に入らなかった」「今までにしたことがないようなミスをしてしまった」といったような話を受験生から聞くことがあります。
二つ目の要因としては、中学入試の出題範囲が「幅広い」ということが挙げられます。特に算数では、問題を見たときにいろいろな解き方を考える必要があります。算数から数学になると、「速さ」も「食塩水」も「割合」も方程式として未知数を決めて立式する……という解き方になるのですが、算数ではそれぞれに一番よい解き方を考えなければなりません。また、理科では「物理」「化学」「生物」「地学」のすべての分野が出題されますし、社会でも「地理」「歴史」「公民」といった分野が出題されます。自分の得意な問題が出題されるかどうかで、結果も大きく変わってしまうことがあるのです。結果として、「偏差値ランク表」では下の方にある学校は不合格になり、上位の学校には合格するということも多く起こるのが中学受験です。今年も、そんな入試結果がたくさんありました。
ただ、自分の力で勝ち取った「合格」という切符、胸を張って「次のステージ」に進んでもらいたいと強く思っています。今まで頑張ってきた努力、培ってきた実力、身につけてきた集中力や気力、困難に立ち向かう力や挫折を乗り越える力……それらは、受験が終わったからといって失われてしまうものではありません。すべて彼ら、彼女たちのなかに残っているのですから。
今年も早稲田アカデミーの受験生たちは頑張ってくれました。このブログは合格実績の報告や宣伝をする場ではありませんので割愛させていただきますが、本当に素晴らしい結果を残してくれました(詳しい合格実績はHPの別ページをご参照ください)。私が担当した受験生たちも、それぞれの進学先を決めて、笑顔で「中1準備講座」に参加してくれています。受験直前期のような教室の緊張感はありませんが、中学校から始まる英語・数学の授業に真剣な目つきで参加してくれています。
中学入試が終われば、小6受験生たちは「次のステージ」へと進むことになります。入試である以上、一番行きたかった学校への進学を決められた方ばかりではありません。実質倍率が3倍の学校であれば、その学校に進学できるのは3人に1人です。進学先が第一志望校でなかった場合、涙をこぼすこともあるでしょう。ただ、中学入試は「合格」か「不合格」か、を決めるゲームではありません。その結果だけがすべてではないはずです。先にも書かせていただきましたが、いままで学び身につけてきたことが、入試が終わったところで消えてなくなるものではありません。確実にこれから先のステージで役に立つはずです。まずは、どのような結果であれ、入試という大きな試練を乗り越えたお子様をほめてあげてください。そして、後ろを振り返るのではなく、前を向いて一歩を踏み出すことが大切です。進学を決めた学校でどのように学び、生活していくかはこれからにかかっているのですから。
入試が終わって、お子様も保護者の皆様もお疲れになっていることと思います。少しゆっくりしていただくのもよいでしょう。今までやりたくても我慢してきたことを、思う存分やらせてあげるのもよいと思います。ただ、そんななかでも、なるべく早く「次の目標」について考え始めることをお勧めします。入試という大きな目標に向かって進んできた毎日は大変だったと思いますが、一方で充実した毎日だったのではないかとも思います。例えば「中学校での英語をしっかりと頑張る!」でもよいでしょうし、将来の大学入試へ目を向けてもよいでしょう。ひとつのゴールにたどり着いた今、そのゴールで立ち止まるのではなく、次のゴールを見据えてスタートを切る準備をしていただく……そんなイメージです。
ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート団体戦の坂本花織選手の演技を見ました。2022年に行われた北京オリンピックの銅メダルの後、4年後の今大会に焦点を合わせて努力をし続けてきたと解説者が話をしていました。受験が終わった生徒たちも、「次」に目を向けてほしいと願っています。
「自分が勉強するんだったら、自分が受験するんだったら、どんなにか楽だろうと思います」。そんなお言葉をお母様から伺うことがあります。「見守る」というのは本当に大変なことだと、私も感じます。受験生の保護者の皆様、本当にお疲れ様でした。
「次の新たなステージ」へと向かうお子様を、これからも応援していってください。私も中学入試を終えた皆様のこれからの活躍を、心より祈り、願っております。
- 2026.02.13 『次の新たなステージへ!』

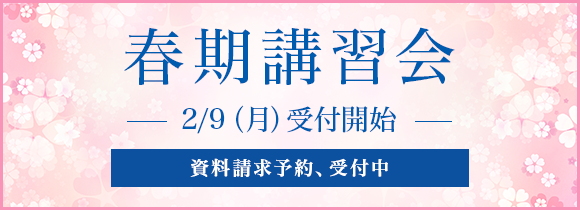
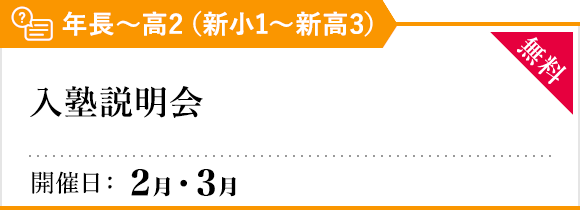


![トップレベル模試 [第1回]](/assets/img/banner/bnr_el_description-exam.png)