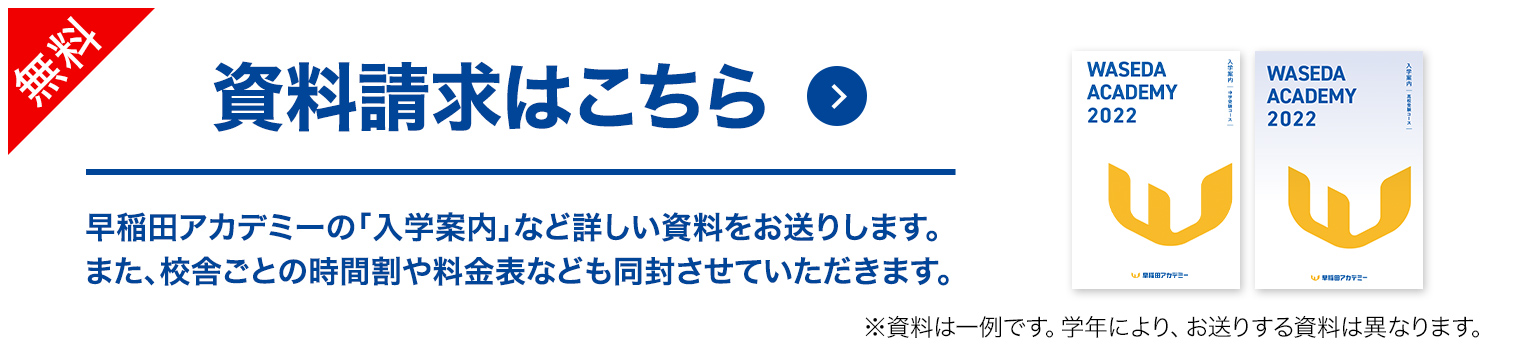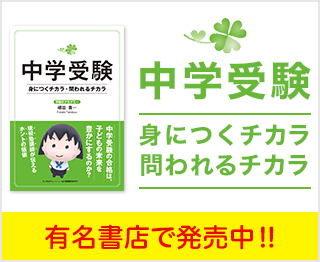『天高く馬肥ゆる秋』
2025.10.29
小学4年生の国語の授業で、「天高く馬肥ゆる秋」という表現が出てきました。秋という季節は、暑くもなく寒くもなく素晴らしい季節だ、という意味の言い回しなのは、保護者の皆様であればご存じでしょう。聞いたことがある生徒もいたようですが、ちゃんとした意味までは理解できていないようでした。
「馬肥ゆる秋」については、秋は収穫の季節でもあり、「食欲の秋」という言葉からもわかるように食べ物が美味しく感じられる時期だという点については、すぐに理解してくれました。一方で「天高く」という部分については、なかなか説明が難しく感じました。「秋の空が高いっていわれるのは知っている?」と質問してみたのですが、残念ながら、ちょっと不思議そうな顔をされてしまいました。 「空はいつでも高いじゃん……」 「夏とあんまり変わらないよ……」 なんていう感じの答えが返ってきたのですが、「そんなことないよ、ちゃんと晴れた日に空を見てごらん」という話をしました。理科の内容になるのですが、秋に空が高く感じられるのにはいくつかの理由があるそうです。一つには空気中の水蒸気が少なくなって「空気が澄んでいる」ため、空の青さ(宇宙の色)が濃く見えるから、だそうです。もう一つの理由は、夏と比べると上昇気流が弱くなるため、入道雲のように地面から近い雲ではなく、空の高いところの雲が多くなるからとのことでした。理科の単元でいうと地学的な内容となり、早稲田アカデミーのカリキュラムでは小学5年生で詳しく学習する内容になります。
「空が高い」といった国語的な表現のなかには、自分自身が実際に感じていなければなかなかわからないことが多くあります。その表現を目にしたり、耳にしたりしたときに「確かにそうだな」と思えることが必要なわけです。そのためには、普段からそういう感性を磨くことが大切になってきます。机の上でテキストとノートを広げて学習するだけではなく、毎日の生活そのものが「学び」になると、私は思っています。特に日本人の感性としては「四季に対する感覚」が大切なものになるのではないでしょうか。
「空が高い」というところから思い出すのは、「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」という正岡子規の有名な俳句です。4年生の学校の教科書にも載っていることがあるようで、この句自体はほとんどの生徒が知っていました。しかし、この句がどういう意味を持っているのか、なぜ有名な俳句なのか、そういったところまで理解できている生徒はいませんでした。そこで、これも秋の澄んだ空気を感じさせる句だ、という話をしていきました。赤い柿の実と青く澄んだ空の対比、鐘の音の澄んだ余韻、そこから感じられる秋の空気感……。さわやかな秋の一日をイメージできるように授業を展開していきました。
「柿くへば……」の俳句の「柿」は秋の季語として使われています。この季語からもわかるように、日本人にとっては「四季」が大きな存在となっているのはご存知の通りです。季語だけではなく、手紙文の「時候の挨拶」などにも季節を表す言葉が使われますし、毎日の挨拶でも気温や天候に関する言葉を交わすのが、日本では一般的です。「今日も暑いですね」「涼しくなりましたね」「雪が降りそうですね」などといった日常生活の中での挨拶は、四季がある日本だからこそだ、という話を読んだことがあります。確かに世界には一年を通して暑い国がありますが、そういった国では「毎日暑いですね」という挨拶が交わされることはないのでしょう。
日本人の季節感には、単に「春夏秋冬」という四季だけではなく、「早春」「初夏」「晩秋」といったような四季をさらに細かく分けるような表現もあります。そしてその言葉にもそれぞれのイメージが含まれています。たとえば「晩夏」という言葉からは、夏の終わりのなんとなくの寂しさが含まれているように。
「夏の夕方にザッと降る雨のことをなんというでしょう?」……この質問に対して、大人であれば多くの人が「夕立」と答えるでしょう。しかし、今の小学生の何割かは「ゲリラ豪雨」と答えてしまうのではないでしょうか。「夕立が降ったあとは地熱が冷まされて涼しくなる」というのも一昔前の話になってしまったようで、現代では「ゲリラ豪雨の後は蒸し暑さが増す」ということもあるようです。夏の風物詩の一つである「浴衣」も、夏の盛りの「盆踊り」や「花火大会」の時期に着るのは暑すぎるので、8月の終わりから9月にかけて「秋祭り」などで着られることが多くなった、という話を聞くこともあります。
地球温暖化の影響が大きいのでしょうか。「夏が長くなった」と感じている日本人が多いという統計を見たことがあります。その反動で「春」「秋」が短くなってしまったという印象もあるようです。「春」も「秋」も日本人の季節感のなかではとても大切な季節なのですが、それが短くなってしまっているということに関しては、若干の寂しさも感じます。
中学入試という視点で考えてみても、国語・社会・理科では、「季節感」を理解しておくことが必要な問題が出題されます。一昔前と比べて少しずつ変わってきている日本の気候や、グローバル化が進み多様な国のイベントが定着しつつある環境のなかで、日本固有の季節感が薄くなってしまっているお子様もいらっしゃるかもしれません。単に入試問題に正解するためだけではなく、昔から育まれてきた日本という国の持つ季節に対するイメージ、そこから生まれてきた文化なども大切にしていってもらいたいと考えています。日本人は季節に寄り添いながら暮らしてきた、そんなふうにも考えています。
- 2025.10.29 『天高く馬肥ゆる秋』
- 2025.10.24 『「わかる」だけではなく「できる」ように……』
- 2025.10.22 『中学入試学習についての「誤解」』
- 2025.10.17 『音読、黙読 ~読解力を育てるための読み方~』
- 2025.10.15 『見る、読む、聞く』
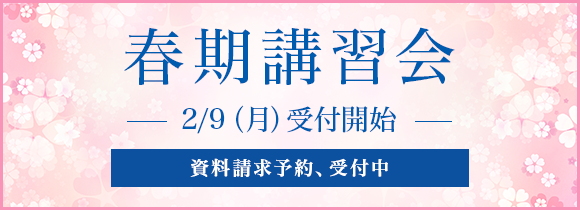
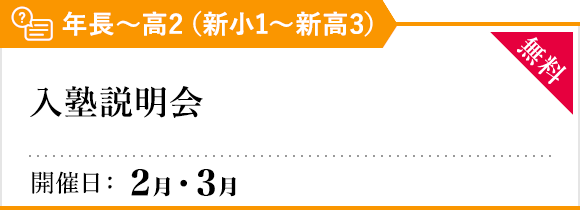


![トップレベル模試 [第1回]](/assets/img/banner/bnr_el_description-exam.png)