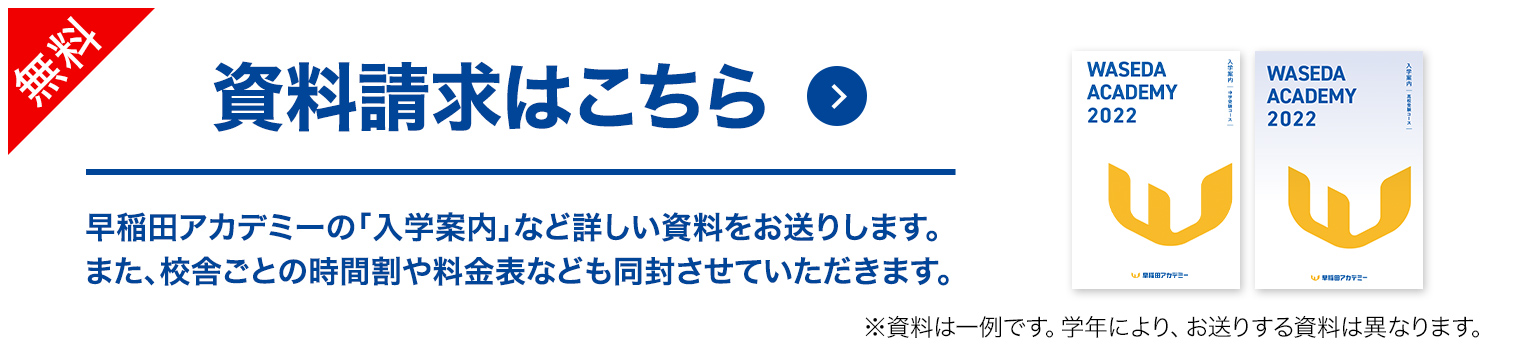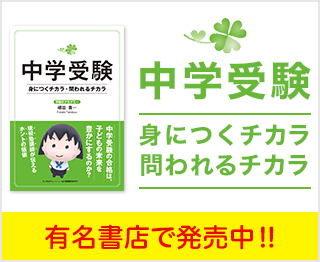『音読、黙読 ~読解力を育てるための読み方~』
2025.10.17
国語の「読解力」というのは、もちろん文章に書かれていることを「読んで理解する」ことです。文章内容を理解するためには、頭のなかで文章を組み立てることが必要になります。塾のテキストやテストの場合、問題を解くために読むという意識が強くなってしまうと、頭のなかに文章の全体像を構築する前に「答えを書こう」という気持ちが先に立ってしまって、この部分がおろそかになってしまうことがあります。それが高学年になって、国語が苦手になってしまう原因の一つとなることもあるのです。
小学校低学年から中学年までは「読み聞かせ」という手法が効果的であるともいわれています。私も小学校1年生から3年生までの国語の授業では、「文章を読み聞かせる」という手法をとることがあります。読み聞かせた文章の内容を、どれくらい「頭の中につくり上げられるか」を確認するという目的のためには、「読み聞かせ」という手法に効果があるのです。テキストはあえて閉じさせたまま、しっかりと聞かせることで「授業を受けるときの集中力を高める」という効果もあります。
物語の「読み聞かせ」は、細かい部分よりも「あらすじ」を理解することがメインです。特に小3・小4くらいまでであれば、細部よりも全体をとらえる力を養う時期ですから、効果的な手法になるのです。ご家庭でも、物語を読み聞かせた後で、登場人物やあらすじについていろいろと質問をすると、文章内容がどれくらい理解できているかを試すことができるはずです。
では、自分で文章を読ませるときには、「音読」と「黙読」のどちらがよいのでしょうか。「音読」にはさまざまな効果があります。文章を読むことに集中させる、声を出すことで元気になりやる気も生まれる、物語の会話文などは感情を込めて音読することで心情理解につながる……などです。特によくいわれるのは、自分の声を自分で聴くことにもなるため、目で追うだけの「黙読」とは異なり、より集中して脳が活性化するというものです。そして音読がうまくできるようになれば、文章を読むことそのものに自信が生まれる。さらに保護者の皆様が聴くことによって、思わぬ「つまずき」に気がつくというメリットもあります。国語が苦手な生徒が「音読」をすると、助詞(て・に・を・は)を間違えることが多いのですが、それを矯正していくと、国語の成績が上がってくることがあります。
一方で気を付けなければならないのは、「音読」をしているときに、「正しく読む」ことだけに注意がいって、字面だけを追いかけてしまい、文章内容の理解にまで至っていないことがあるという点です。音読をさせた後に、何が書いてあったかを確認してみるとわかるはずです。同じような文章を読み聞かせたときと比較して、理解度が低くなってしまうことが往々にしてあります。文章全体をしっかりと理解するという読解力向上だけを考えた視点でとらえると、「音読」よりは「読み聞かせ」の方が効果のあるケースもあります。
最終的にはもちろん「黙読」をして、文章全体を頭の中に構築し、さらに細部にも注意が払えるような読み方が必要になってきます。「黙読」をしているのに、頭のなかでは「音読」と同じような状態になっていて、その結果最後まで読んでも何も頭に残っていない……、そんな読み方にならないようにしてあげなければなりません。そのためには、いまお子様がどのように文章に触れているかを確かめて、その段階で一番効果的な読み方をさせていくことが大切なことなのだとお考えください。
- 2025.10.17 『音読、黙読 ~読解力を育てるための読み方~』
- 2025.10.15 『見る、読む、聞く』
- 2025.10.10 『「制御性T細胞」と「金属有機構造体」』
- 2025.10.08 『入試過去問の使い方』
- 2025.10.03 『親の関わり方 ~「はげます」の重要性~』
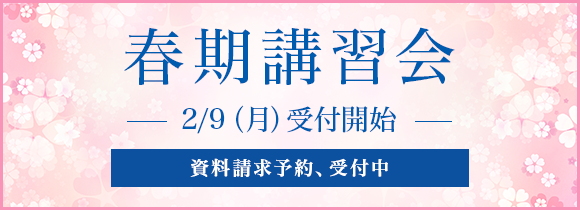
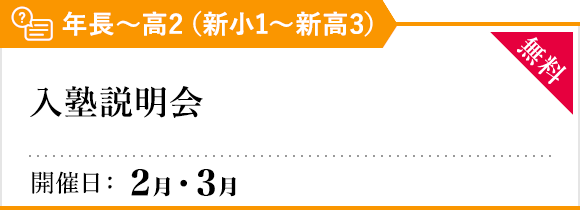


![トップレベル模試 [第1回]](/assets/img/banner/bnr_el_description-exam.png)