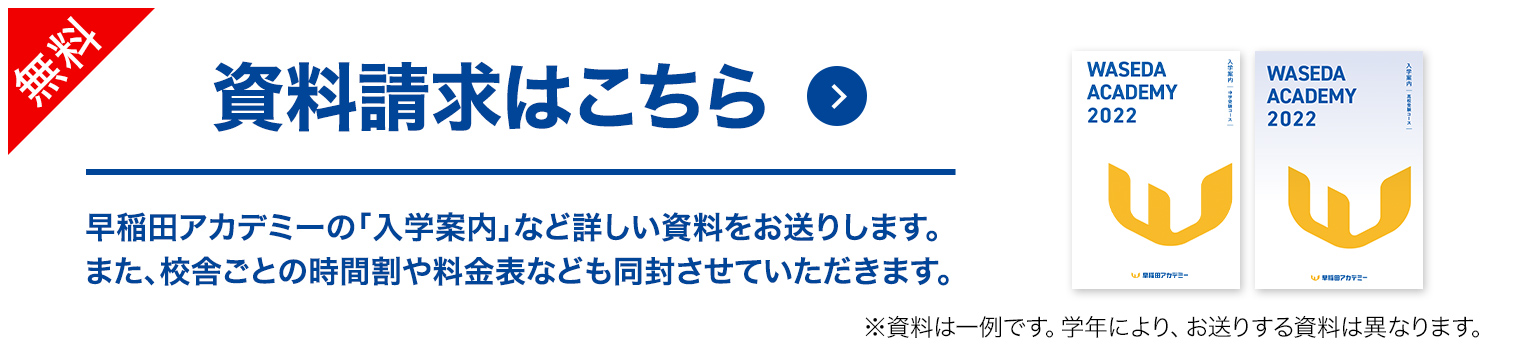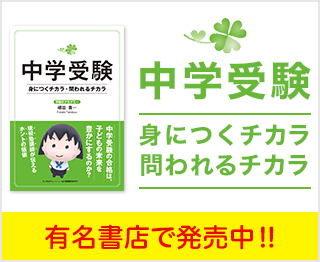『入試過去問の使い方』
2025.10.08
秋に入り、小6受験生たちは「過去問演習」の時期に入っています。
早稲田アカデミーでは「過去問演習進行表」という冊子を配布し、志望校の過去問演習を計画的に実施させています。また、担当講師がその冊子でチェックをするような体制を組んでいます。「やりっぱなし」にならないよう、得点だけではなく、解いた内容と間違えた問題を分析させることで、次につながるようにしています。今回は入試過去問について。
まず、受験生によく話をしていることなのですが、私は、入試問題にはそれぞれの学校が「どのような生徒を求めているか」というメッセージが込められていると考えています。「うちの学校で学ぶためには、こういう問題が解けるようになっている必要があります」というイメージです。ですから、学校の入試問題を見ることで「お子様に合っている学校かどうか」もある程度わかるわけです。もちろん入試問題だけではなく、学校全体を見ることの方が大切なのですが。
入試過去問題を解く第一の目的は、「出題傾向をつかむ」という点にあります。当たり前のことですが、その学校で過去問と同じ問題が出題されることはまずないでしょう。そう考えれば、「二度と出題されない問題」ということもできるわけです。ただ、その根底にある出題方針や出題傾向が大きく変わることはありません。もちろん、年によっては、大きく傾向を変えてくる学校がないわけではありませんが、その場合は「学校説明会」などで事前に説明があるケースも多くなっているようです。この「出題傾向をつかむ」という目的を意識して過去問に取り組まなければ、無駄な学習をしてしまうことにもなりかねません。
学校によって出題傾向はさまざまです。例えば、算数のテストで易しい計算問題から順に難しくなるように並んでいて、最後に一番応用的な問題があるというスタイルの学校もあれば、大問の1番から非常に手応えのある問題を出題してくる学校もあります。国語では、漢字や知識を独立した大問として出題する学校があれば、出題文中に漢字・知識の問題が混ぜられている学校もあるわけです。解答スタイルにしても「記述」「客観選択式」などがあるのはご存じのとおりです。
その学校がどのような問題を出してくるのか、事前にある程度知っている状態で入試本番に臨むのと、なにも知らずに臨むのとでは、結果が大きく異なることはご理解いただけると思います。
過去問に取り組んでいたとしても、出題傾向が大きく変わったときには、入試会場で「どうしよう」という不安を感じてしまう受験生もいます。そのため、「出題傾向が大きく変わったとしても、そのときはすべての受験生が同じ条件になるのだから、落ち着いて解きなさい」と受験生には事前に話をしています。「あっ、変わった!」と思ったときに、動揺するか落ち着けるかで、実力が発揮できるかは変わってくるものです。
入試過去問を学習するときに注意していただきたいポイントがあります。それは模範解答や解説の扱い方についてです。一番気を付けていただきたいのは、「その模範解答は誰が作成したものなのか」という点です。出題した学校が作成したものであれば、その解答は非常に大切なものになります。出題内容に対しての学校側の解答要求レベルを示すものになりますので、特に記述問題などは、どこまで書けばよいのかを把握する大きな基準となるわけです。一方で、学校ではなく入試過去問題集を作成している出版社が作成をした模範解答もあります。この場合、解答自体に大きな間違いがあるわけではありませんが、学校が要求しているレベルとは異なる場合があります。学校以外で作成された模範解答は、学校が要求している解答レベルよりも高いものになっているのが一般的です。記述などは「誰が見ても正解」となるレベルの解答になっていますので、小学生はもちろんのこと、大人でも書けないようなレベルのものになっていることがあります。その模範解答を基準に採点をしてしまうと、記述部分はすべてバツになってしまい、お子様のモチベーションが下がったり、保護者の皆様の不安が募ったりということにもなってしまいかねません。
また、解説についても注意が必要です。「算数」の問題の解説なのに一部「数学」的な考え方が書かれていたり、もっと簡単に解けるのに複雑な解き方が書かれていたり、というようなケースもままあります。いずれの場合も、不安な点があればお子様を担当している塾の先生にご相談いただくのがよいでしょう。
中学入試において、「満点」を取らなければ合格できない学校はありません。合格最低点は公表されている学校もあれば、されていない学校もありますが、概ね予測はできるはずです。入試過去問演習を進めるなかで、自分の「合格のための設計図」をイメージすることが合格への秘訣となります。
国語・算数・社会・理科の4科目が均等配点(各科目100点満点)で400点満点の学校があったとします(実は、均等配点の学校は少ないのですが……)。その学校の合格最低ラインが約6割だったとしましょう。その場合、240点を最低目標としてとれるように考えていくのが「合格のための設計図」です。非常にバランスのよい受験生であれば、全科目60点が目標点となるわけですが、そういったケースは非常に稀だと思います。得意な科目では70点を目標とし、苦手な科目では50点が目標となることもあるわけです。そう考えると、各科目の問題への取り組み方も変わってきます。それぞれの科目で出題される問題のなかで、どの問題に注力するか、どの問題を解き切るか、どの問題を後回しにするかという判断も必要になってくるわけです。
- 2025.10.08 『入試過去問の使い方』
- 2025.10.03 『親の関わり方 ~「はげます」の重要性~』
- 2025.10.01 『助詞の使い方を意識する』
- 2025.09.26 『ことわざの語源』
- 2025.09.24 『読むスピード、解くスピード』
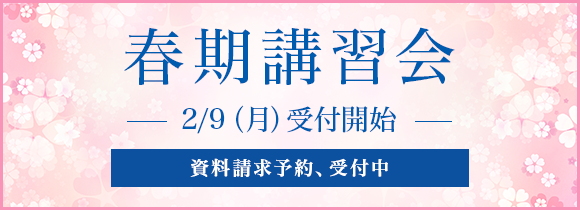
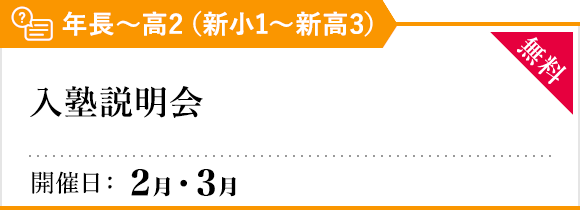


![トップレベル模試 [第1回]](/assets/img/banner/bnr_el_description-exam.png)