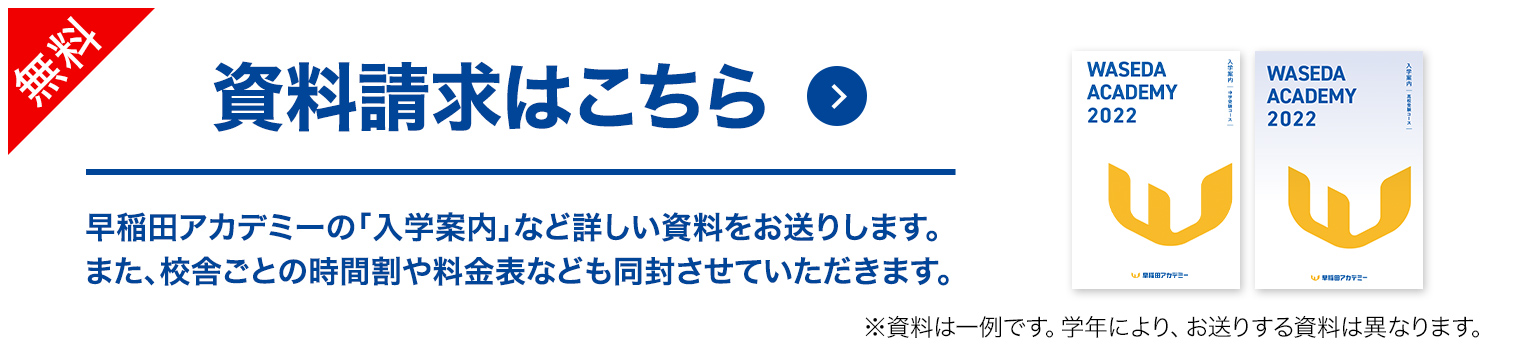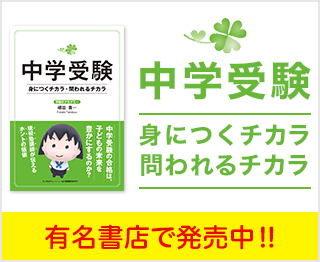『見る、読む、聞く』
2025.10.15
最近の中学入試では、「グラフ・図表」を読み取る問題が増えてきています。以前から理科や社会では「グラフ・図表」も出題されていましたが、単にそれを「読み取る」だけではなく、そこから読み取れたことに関して考えさせるタイプの問題が多くなっています。理科・社会だけではなく、国語でも「グラフ・表の読解問題」が出題されることがあります。
これらの問題で問われる「グラフを読み解く力」は、広い意味では「読解力」ということもできるのですが、文章読解とは違い、グラフの「どこを見るか、どこに着目するか」という視点が必要になります。そういう意味では、算数のダイヤグラムの問題などにもつながってきます。
算数の「図形問題」を解くためには、「見る力」が必要になってきます。特に「立体図形」は生徒によって得意・不得意の差が大きくなる単元ですが、「図形を見る力」の差が大きく影響しているように思っています。「立体図形」を平面上に表す場合、いくつかの種類の書き方がありますが、中学受験においては「見取り図」が多く使われます。「投影図」が使われることもありますが、頻度はそれほど多くありません。「見取り図」を見たときに、頭の中で「立体をイメージできるかどうか」が、立体図形が得意になるか、不得意になるかの大きな分岐点になるように感じています。
「見取り図」にしても「投影図」にしても、実際には「立体」である図形を、それぞれの「ルール」に従って「平面」に描き表しているものですので、「ルール」を理解すればよいことになります。しかし、それだけでは実際に「見えてくる」ようにはなりません。必要なのは「立体を見る感覚」であり、この感覚は小学校低学年のときからのトレーニングで身につくものです。比較的早いタイミングで「立体感覚」が身についてくるお子様もいますし、なかなかうまくつかめないお子様もいます。繰り返しトレーニングしていくことが必要な部分だとお考えください。特に低学年においては、立体図形を「見る」だけではなく、「自分で描いてみる」という練習も効果があります。ご家庭で「立方体」を描かせてみるのも面白いトレーニングになるはずです。
さて、小学生の学習における「見る力」「視野・視点」というテーマで考えるときに、私は大きく二つの力をイメージしています。「全体を大きく俯瞰する力」と「細部に着目する力」の二つです。
国語の読解問題でお考えいただくとわかりやすいのですが、「主題・要旨」などの文章全体をとらえて考えるタイプの問題と、「指示語・接続語・表現」などの細部を精読して考えるタイプの問題があります。学校によってどちらのタイプの比重が大きいかは変わってくるのですが、お子様によってもどちらの問題が得意かの違いがあります。「どちらがよいか」ということではなく、両方の視点をしっかりと使い分けることが必要になりますし、両方の視点があることを意識してトレーニングを積み重ねていくことが大切だとお考えください。
次に「聞く・聴く力」について。学力を伸ばしていくためには、「聞き取る」力がとても大切です。保護者会や講演会では、「授業を受ける力」を伸ばすことが学力向上につながる、ということをよくお話ししています。「授業を受ける力」として大切なのは、授業で先生が話しているなかから、重要な点をしっかりと聞き取って理解するという点です。もちろん先生は「重要なポイント」を強調して話をするのですが、小学生の場合、必ずしもそこが頭に残っているわけでもありません。ある程度のトレーニングをしていけば、どこが大切かを「聞き分け」て、そこをしっかりと覚えておくことができるようになっていくものです。しかし、経験やトレーニングが足りていない場合、なかなかそれがうまくいきません。中学校や高校に進学すれば、授業内容はより高度になり、密度も高くなりますので、小学生の間に「聞く力」を鍛えておくことが必要になるのです。学校の授業よりもスピードが速く、密度も高い進学塾での授業で身につけるべきことは「学習内容」だけではなく、この「学習の仕方」「授業の受け方」であり、それが次のステージで学ぶ力につながると思っています。
- 2025.10.15 『見る、読む、聞く』
- 2025.10.10 『「制御性T細胞」と「金属有機構造体」』
- 2025.10.08 『入試過去問の使い方』
- 2025.10.03 『親の関わり方 ~「はげます」の重要性~』
- 2025.10.01 『助詞の使い方を意識する』
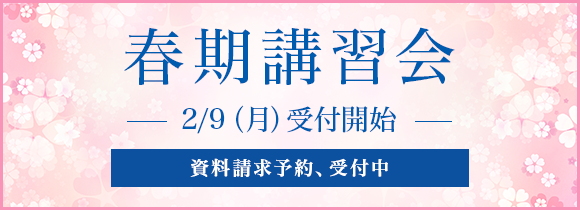
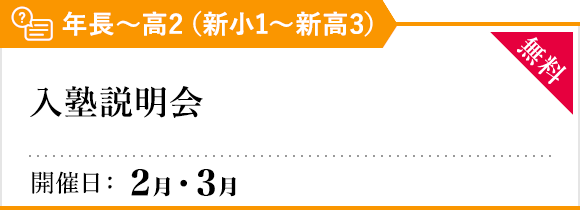


![トップレベル模試 [第1回]](/assets/img/banner/bnr_el_description-exam.png)