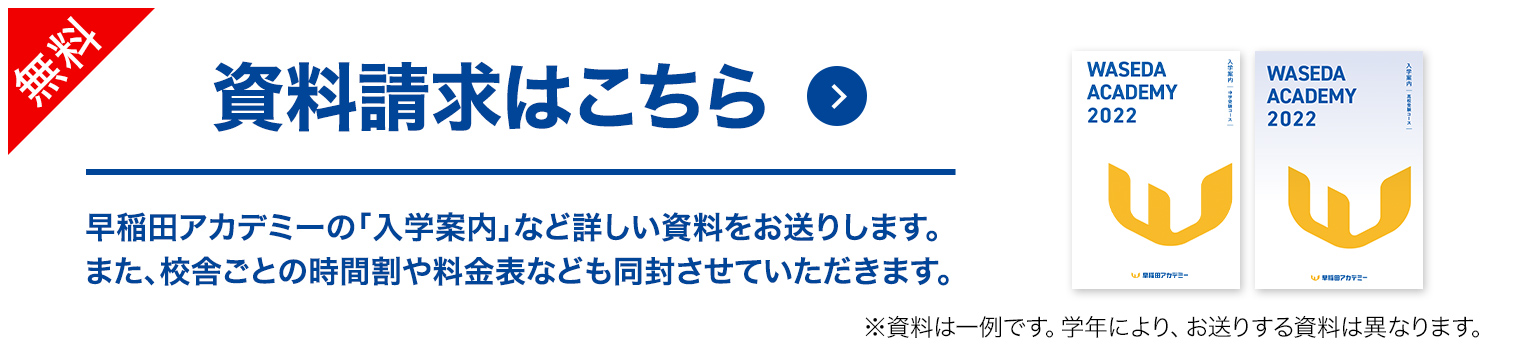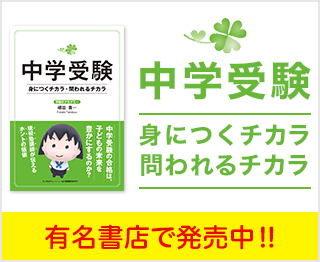『「わかる」だけではなく「できる」ように……』
2025.10.24
前回の記事では「中学受験学習における誤解」というテーマで書かせていただきました。今回も保護者の皆様が「誤解」しやすいポイントについて。
よく「わかる」と「できる」は違う、という言葉を耳にします。大人になれば、「わかった」ことはすぐに「できる」のが普通です。さまざまな経験を積んでいるため、その経験を新しく学んだことにも生かすことで、アウトプットすることが容易にできるはずです。しかし、小学生の場合は違います。「わかった」ことを自分で「できる」ようになるためには、自分のなかでしっかりと理解し、使いこなす過程を考えて、試行錯誤をすることが必要になります。
年齢が上がってくれば、「わかる」と「できる」の距離は縮まってきますので、中学生や高校生対象の塾・予備校であれば、「わからせる」ことのみでも、生徒は自分から「できる」ようになってくれます。しかし、小学生の場合、「わかった」だけではなかなか「できる」ようにはなりませんから、その視点を持って指導をすることが必要になってきます。そういう点において、小学生の指導をするうえで一番大切なことは、「わからせよう」と考えながら指導するのではなく、「できるようにする」ことを意識して指導することだと、私は考えています。
さて、中学受験カリキュラムの場合、その週に出てきた内容をすべて「できる」ようにするのはなかなか難しいことです。小学校の教科書のように、その学齢の生徒が「できる」ことを前提につくられている教材であれば、「理解できれば、そのままできるようになる」ものですが、中学入試に向けた教材やテキストは違います。中学入試カリキュラムは、その学齢の生徒にとってはハードルが高く、「理解できていても、自分でできるところまではいかない部分=積み残し」が前提となっているカリキュラムです。ですから、その週においては「なんとなくわかっている」レベルでかまわない部分も多いわけです。逆にいえば、どこまでを「できる」ようにするのかを考えることが大切なのです。この判断はクラス・生徒によってさまざまです。早稲田アカデミーでは隔週(小6は毎週)で単元テストを実施しています。1週間もしくは2週間で学んだ内容の定着度を測るテストですから、「頑張って勉強したら、テストでもいい点がとれた」という結果はお子様の「やる気」に直結することになります。そういった場合、テストで出題されそうな問題は「できる」ようにしてあげることを意識して指導することもあるのです。
早稲田アカデミーのカリキュラム(四谷大塚の予習シリーズカリキュラム)では、同じ単元の学習が、ある程度の期間をおいて何度も出てくるように組まれています。この点を考えると、次に同じ単元が出てくるときに、どこから学習が始まるのかを理解しておくことが必要になってきます。言い換えれば、次に出てくるときまでに「できる」ようになっておかなければならない部分を把握しておくことが重要なのです。この点は保護者の皆様にとってはなかなか難しい部分だと思います。ご家庭で指導される際に、「今どこまでできるようにしておかなければならないか」などで悩まれた場合は、担当講師にご相談いただくのがよいでしょう。
塾での授業が終わった後、お迎えのお母さまが「今日の授業はどうだった?」とお子様にお尋ねになっている場面を目にすることがあります。多くの場合、お子様は「うん!わかった!」というようなことをお答えになるでしょう。ところが、家に帰ってきて宿題をやっているのを見ると、問題を前にして鉛筆が止まってしまっている、どうも解けていなさそうだ……。そんなことがよくあるのではないでしょうか。
お子様の「わかった!」という言葉はなんだったのでしょうか。お母さまを安心させるための言葉という部分もあるかもしれません。ただ、本当に授業中に「わからなかった」のだとするならば、それなりの反応があったはずです。この時点でお子様は本当に「わかって」いたのだとお考えください。
家庭学習で「できていない」場面を目にしたお母さまからご連絡いただくことがあります。「先生、宿題ができていないのですけれど、授業中にちゃんと聞いていますか?子どもは『わかった』と言ってはいるのですが、本当は『わかっていない』のじゃないかと心配で……」、そんなお話です。私からは「授業中はちゃんと聞いていますし、その場ではきちんと考えて答えも出せていました。ですから、ちゃんと『わかって』はいます。ただ、『わかった』ことが自分で『できる』レベルにまではいっていない部分がある、とお考えください」というようにお答えしています。保護者の皆様に単に安心していただくようにお答えしているのではなく、お子様の状況をきちんとお伝えするようにしています。
そして、さらに付け加えるのは「『できていない』ことを『わかっていない』と、お子様には言わないでください」という話です。お子様のなかでは、なんとなくでも「わかった」と思っていたことに関して、お父さまやお母さまから「わかっていない」と決めつけられてしまうと、自分が「わかった」と思っていた気持ちが揺らぎ始めてしまいます。ときには自己肯定感を失うことにもつながりかねません。
- 2025.10.24 『「わかる」だけではなく「できる」ように……』
- 2025.10.22 『中学入試学習についての「誤解」』
- 2025.10.17 『音読、黙読 ~読解力を育てるための読み方~』
- 2025.10.15 『見る、読む、聞く』
- 2025.10.10 『「制御性T細胞」と「金属有機構造体」』
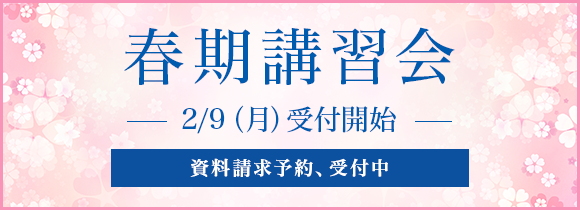
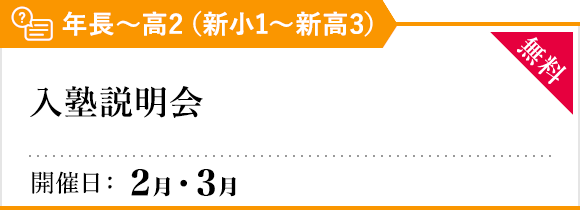


![トップレベル模試 [第1回]](/assets/img/banner/bnr_el_description-exam.png)