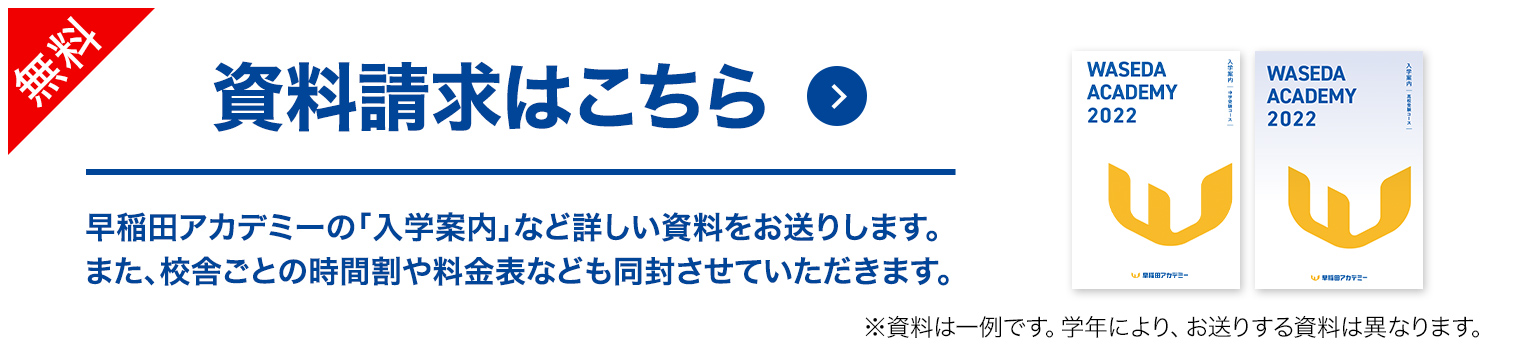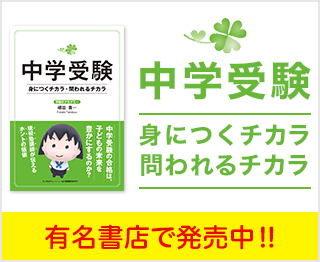『中学入試学習についての「誤解」』
2025.10.22
先週の金曜日(10/17)に早稲田アカデミー晴海校ホールで「クローバーセミナー」を実施いたしました。今回も多くの皆様にご参加いただき、本当にありがとうございました。晴海校は近隣の「都営大江戸線・勝どき駅」から徒歩10分程度のところにあり、千葉県や埼玉県の遠方の校舎に在籍いただいている方にも多くお越しいただきました。
今回は「学習への親の関わり方」というテーマで、前半は「中学入試は親子の受験」と題して、中学入試学習を進めていく上で、保護者の皆様に意識しておいていただきたいことをお話しいたしました。後半は、より具体的に「日常生活の中での接し方」「自己肯定感を高める」「精神的成長を促す」という内容で、私がこれまで担当してきた生徒の実例も交えながら、お話しさせていただきました。
セミナーの中で「大切なポイント」としてひとつお伝えしたことは、「中学入試へ向けた学習の進め方をしっかりとご理解いただく」という点です。小学生の学習方法は、中学生や高校生とは違います。また、中学受験の問題や出題傾向も昔からは大きく変わってきています。その点を保護者の皆様がご理解いただくことで、お子様の学習はスムーズに進んでいくはずです。逆にその点を「誤解」してしまうと、お子様も保護者の皆様もつらくなってしまうのです。
「学習単元が一週間ごとに変わる理由」「テキストの使い方」「偏差値の見方・考え方」など、中学受験に特化した理解が必要になる点、もしくは保護者の皆様が「誤解」してしまう可能性が高い点がいくつかあります。そんなお話をさせていただきました。実は「小学生のテスト・中学受験へ向けたテストの位置づけ」もそんなポイントの一つです。今回は「中学受験へ向けたテスト」について。
小学生のためのテストにはいろいろな目的があります。中学生以上になってくると「現状の学力を測り、試す」というのがほとんどのテストの大きな目的になるのですが、小学生のテストはそればかりではありません。
小学校6年生になると志望校判定のための模試が実施されます。四谷大塚が主催するものであれば「合不合判定テスト」「志望校判定テスト」というテストがありますし、そのほかの主催母体でもいくつかの合格可能性判定テストが行われています。これらのテストは、中学生以上のテストと同じ「現状の学力を測り、試す」ということが主目的になり、結果を分析することで、今後の学習指針を考えるという形で活用していくものになります。
一方、テストを受けることそのものが「学習内容の定着」につながり、直接的に学力向上・成績向上につながるテストもあります。早稲田アカデミーの小4で実施している「カリキュラムテスト」や四谷大塚の「週テスト」(早稲田アカデミーの土曜YT講座)のような、毎週(もしくは隔週)の単元テストがこれにあたります。テストを受験することで学力が伸びるメカニズムに関しては、以前の記事でも触れさせていただいたことがありますので、ここでは割愛させていただきます。より難度の高い問題を自分で解けるようになるためには、単元テストが必要なものなのです。早稲田アカデミーの志望校別クラス(NNクラス)で実施されている「確認テスト」も、この目的を持ったテストになります。
一方、塾での毎回の授業時に実施される「漢字テスト」や「計算テスト」にはまた別の意味があります。これらのテストは、家庭学習をしっかりやらせるという目的や、授業に向かうモチベーションを高め集中させるといった目的、などのために実施しています。
さて、11月3日(月祝)には「全国統一小学生テスト」が行われます。このテストの大きな意味は「学習へ向かうきっかけ」ということになるでしょうか。出題される問題は多岐にわたりますし、受験される方の学習状況や背景も様々です。非常に大きな範囲で考えれば「いまの実力を測る」ということもいえるのですが、それよりもこのテストを受験することを「きっかけ」として学習に対する前向きな気持ちをつくるものとお考えいただければと思います。四谷大塚の予習シリーズカリキュラムで学習されている方も、テスト内容はカリキュラムと直接の関係はありませんし、また小学校での学習内容とも異なっています。「学力の全国大会」として、全国のライバルたちと同じ時間に同じ問題で競い合う、そんなイメージで楽しんで受けていただければと思います。
- 2025.10.22 『中学入試学習についての「誤解」』
- 2025.10.17 『音読、黙読 ~読解力を育てるための読み方~』
- 2025.10.15 『見る、読む、聞く』
- 2025.10.10 『「制御性T細胞」と「金属有機構造体」』
- 2025.10.08 『入試過去問の使い方』
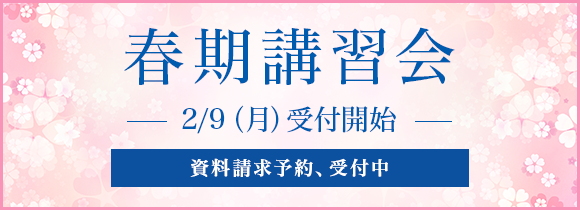
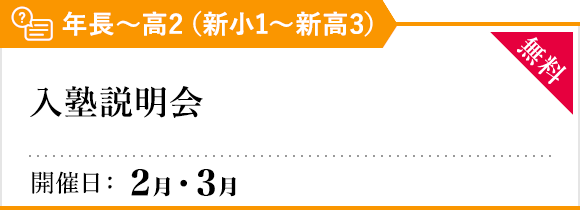


![トップレベル模試 [第1回]](/assets/img/banner/bnr_el_description-exam.png)