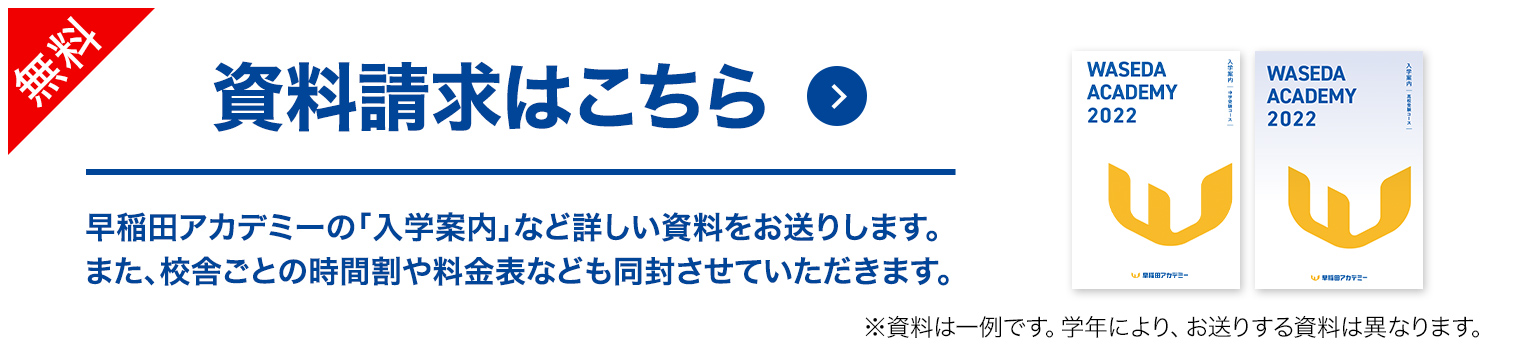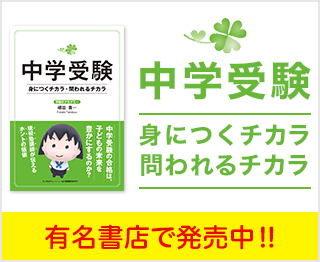『親の関わり方 ~「はげます」の重要性~』
2025.10.03
10月17日(金)に、早稲田アカデミー晴海校で「クローバーセミナー」を実施させていただきます。今回は「学習への親の関わり方」というテーマで、いくつかの切り口から「中学受験学習」を進めていくお子様に対する、「親の関わり方」をお話しさせていただく予定にしております。
セミナーに向けては、どのような内容をどのような構成でお話しすればよいのかを、いろいろと考えて準備します。90分という時間のなかで、何をどのようにお伝えすればご参加いただいている保護者の皆様にとって有益だろうか、そんな視点で用意していたテーマから取捨選択をして構成を考えていきます。結果として「用意はしていたけれど、今回は外したテーマ」というのが、いくつも出てきます。それらはこのブログでご紹介しているのですが、今回の記事もそんな内容です。「お子様への関わり方」として大切な「ほめる・しかる・はげます」というテーマで。
子育てにおいては「ほめる、しかる」が大切であるとよくいわれます。さらに、塾も含めた小学生の習い事では「ほめる、しかる、はげます」という三つの要素が必要になるともいわれるようです。この点に関しては、私も全面的に賛成です。小学生にとっては、親を含めた周りの大人からの「評価」がとても気になるものですし、大人からの「声掛け」によって気持ちが大きく上下するものだと思うからです。
進学塾でも、子どもへの「声掛け」がうまい先生は成績を上げることができる、と研修で教わります。ちょっとした「声掛け」によって生徒のやる気を引き出し、結果として前向きに学習に取り組ませることができるようになるからでしょう。「成績を上げて志望校へ合格させること」が進学塾講師の役割だとすれば、「教えることがうまい」というのももちろん必要なことですが、「生徒のやる気を引き出す」というのはそれ以上に大切なことでもあると、私は考えています。
「声掛け」や「ほめる・しかる」がうまい、というのはどういうことなのでしょうか。私は「子どもの気持ち」を考えて接することが、その基本にあると考えています。ほめて欲しいときにほめる、しかられるだろうなと感じているときにしかる、そんなイメージです。逆を考えてみればよくわかるはずです。テストで好成績をとって「ほめてほしいな」と考えているときに、逆にしかられてしまえば、ちょっと上向いていた気持ちは一気にしぼんでしまうことでしょう。悪い成績で「しかられる」と感じているときに、なにも言われなければ、「見捨てられた」という気持ちになってしまうこともあるかもしれません。ご家庭でお子様に接するときにも、ご自身がどのような気持ちであるかということよりも、お子様の気持ちに視点を移して接してあげるだけで、「ほめる・しかる」はより効果的なものになると思います。
さて、「ほめる・しかる」と比べると難しいのが「はげます」です。まずお子様の心的状況に視点を据えて、「はげます」必要がある場合を考えてみましょう。それは、お子様の気持ちは沈んでいるときのはずです。努力をしたのに結果が出なかった、そんなときではないでしょうか。そこでどのように接すればお子様の気持ちは上向きになるのかを考えていただきたいのです。
はげますための言葉として、パッと思いつくのは「頑張れ」「頑張って」という便利な言葉です。ただこの言葉は、私にとっては「はげます」ための言葉ではなく、単なる「あいさつ」のような言葉です。校舎にやってきた生徒に「よし、今日も頑張ろうね」と声を掛ける、そんなイメージです。落ち込んでいるお子様の場合、そのほとんどはすでに一生懸命「頑張っている」はずです。それでも結果が出ない、なかなかうまくいかない、そんな状況でしょう。そんなときに、さらに「頑張れ」という言葉をかけたとしても、気持ちが前に向くはずはありません。ときには「もうこれ以上頑張れない」という気持ちになって、より深く落ち込んでしまう可能性もあると思うのです。
では、効果的に「はげます」ためには、どうしたらよいのでしょうか。まず必要なのは、やはり子どもの視点に立って「共感」することだと考えています。「成績が上がらない」「うまく家庭学習が進まない」という事実だけではなく、そこから生まれてくる気持ちをとらえて、そこに「寄り添う」というようなイメージです。単に落ち込んでいるというだけではなく、そこにはいろいろな気持ちが生まれているはずです。「何をやってもうまくいかないイライラ」「自分に対する不甲斐なさ」「親の期待に応えることができない情けなさ」「自分には難しい(と思われる)勉強をしなければならない負担感」「友人にはできる問題が解けない悔しさ」などなど……。そこをしっかりととらえることが、「はげます」ためのスタートラインだと思うのです。そのスタートラインがズレてしまっては、掛ける言葉が心の奥まで届くことはないはずです。
気持ちに「寄り添う」ことができると、お子様は安心してくれるはずです。「自分のことをわかってくれている、いつも応援してくれている」という安心感は、どんな言葉よりも、強い「はげまし」になるのだと、私は考えています。
- 2025.10.03 『親の関わり方 ~「はげます」の重要性~』
- 2025.10.01 『助詞の使い方を意識する』
- 2025.09.26 『ことわざの語源』
- 2025.09.24 『読むスピード、解くスピード』
- 2025.09.19 『本気でやる子を育てる ~401の想い出~』
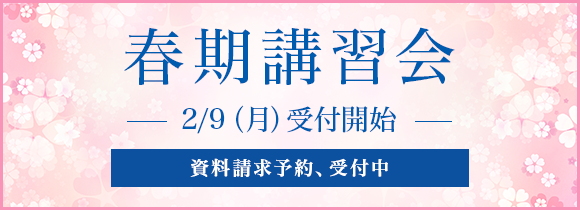
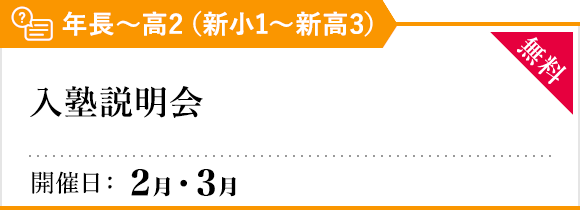


![トップレベル模試 [第1回]](/assets/img/banner/bnr_el_description-exam.png)