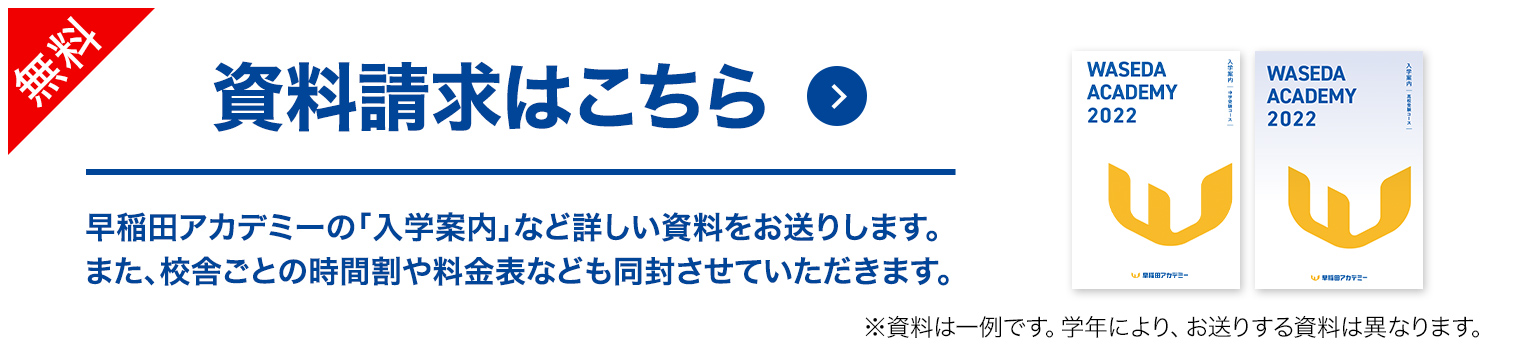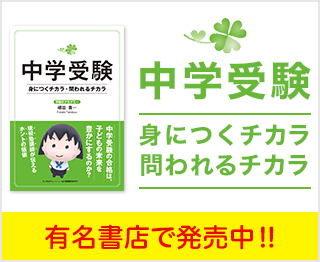『読むスピード、解くスピード』
2025.09.24
国語の授業で生徒たちの「読解スピード」を試すことがあります。「先生の合図でテキストを開いて、読み始めること。急いで読まなくてよいから、丁寧にしっかりと読むこと。読み終わったらテキストを閉じて、手を挙げなさい。では、よーい、はじめ!」という話をしてから読み始めさせます。
手が挙がった順をチェックしておくのですが、国語が得意な順(国語の成績順)にはなりません。実は、速く読み終わる生徒は、国語が苦手な生徒の方が多いのです。全員が読み終わった時点で、問題に取りかからせます。これも「よーい、はじめ」の合図でスタートさせて、終わった生徒は挙手をさせます。「読むのが速かった生徒」と「問題を解くのが速かった生徒」はまったく違う結果となります。逆転していることの方が多いのです。国語の文章問題では、「読むスピード」と「解くスピード」は一致しないわけです。
「国語のテストでは、いつも時間が足りなくなる」という生徒の場合、この「解くスピード」が原因となっている場合が多くあります。しかし、自分では「読むのが遅いから」と感じてしまっていて、急いで読もうとしてしまうことがあります。急いで読もうとすると、文章全体が頭に入りません。極端な場合、字面を目で追いかけているだけで、ほとんど文意を理解していない場合もあるでしょう。結果として、設問を解くのにより時間がかかってしまうことになるわけです。
文章題の設問を解く場合、問われていることに対して「だいたいの解答を頭のなかでイメージする」ことがスタートラインとなります。選択肢問題でも記述式問題でも、まずはなんとなくイメージするのですが、文章の内容が頭に入っていないとそれができません。「ゼロ」の状態で文章に戻って、文章を読みながら「イチ」から考えるので、当然時間がかかってしまうわけです。
「文章全体が頭に入っていない」という状態の場合、「解くスピード」が遅くなることに加えて、正答率も低くなります。選択肢問題では「見当外れ」なものを選んでしまったり、記述問題では「表面的な浅い記述」になってしまったり、ということが起こってきます。そして、一番影響が出やすいのが「空欄補充問題」の解答です。「本文中の空欄(もしくは設問文中の空欄)を、本文中の語句を使って埋めなさい」というタイプの問題です。この種の問題は、「たぶん、こんな内容の言葉が入るはず」と推測し、「たしか本文中のあの辺にそういう言葉があった」と考えて、探しにいくのが正しい思考の筋道です。
しかし「文章が頭に入っていない状態」だと、本文全体を、一つの言葉を探しながらウロウロすることになってしまいます。さらにいえば「探すべきもの」のイメージができていない状態で探すわけですから、そう簡単に見つかるはずはありません。制限字数が決まっている場合は、その字数だけを手掛かりに探したりすることもあるでしょう。偶然、見つかってマルがつくことがあるかもしれませんが、それは正しい筋道をたどった正解とはいえないわけです。お子様の解答用紙をご覧になって、「空欄補充問題」が空欄で残っている場合や、テスト後に「空欄補充で時間がかかった」という場合などは、「文章が頭に入っているかどうか」を確認していただくのがよいかもしれません。
文章内容が頭に入っているかをチェックするために、小3から小4の授業で行う方法があります。ご家庭でもできると思いますので、ご紹介します。文章を読み終えたところで、テキストを閉じさせて、文意に関する質問を重ねていくという方法です。物語文であれば、登場人物から場面構成、人物同士の関係などから始めていきます。説明的文章であれば、文章のテーマ(話題)を「何について書いてある文章だった?」という質問から聞き始めます。ツバメの生態を具体例にして、生物全体の環境について書かれている文章の場合など、「ツバメについての文」という答えが返ってきたりもするのですが、それをきっかけに「具体例」と「結論」についての文章構造理解につなげていったりすることもあります。よろしければ、ご家庭でもお試しください。特に国語の文章問題を苦手としているお子様には効果があると思います。
国語の講師が授業中に生徒を観察する視点として、文章問題を解いているときの、生徒の「目の動き」と「手の動き」に注意するという方法があります。「文章をどれくらいの速さで読んでいるのか」という点は目の動きを見ているとわかります。さらに、どの問題を考えているときに、文章のどのあたりに目をやっているのか、文章のどの辺りに線を引こうとしているか、などを見ているわけです。
算数の場合は、思考過程や解答を出すまでの処理方法は、ノートに残りますので「手の動き」だけでわかります。しかし、国語の場合は思考過程まで解答用紙には残りません。特に選択肢問題をどのように選ぼうとしているかは、「目の動き」を見るのが一番効果的なのです。それぞれの選択肢をどれくらいの速さで読んでいるか、どの選択肢のどこに「印」をつけているか、本文のどこを読み直して考えているか、もしくは本文には目をやらずに選択肢だけで選ぼうとしているか……。そんなところを気にしながら、生徒を見ています。とはいっても、クラス全員の生徒にすべて目を配るのはなかなか難しいのですが。できましたら、ご家庭でも国語の文章題を解いているお子様の「目の動き」に注目していただければと思います。
- 2025.09.24 『読むスピード、解くスピード』
- 2025.09.19 『本気でやる子を育てる ~401の想い出~』
- 2025.09.17 『50周年』
- 2025.09.12 『時間効率を意識した学習を』
- 2025.09.10 『ブラッドムーン』
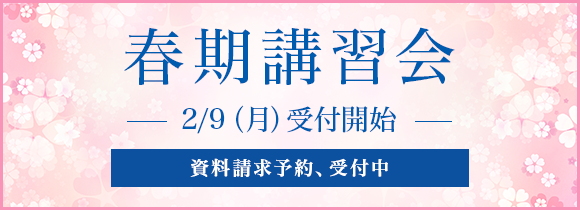
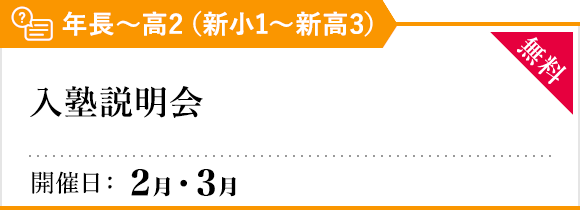


![トップレベル模試 [第1回]](/assets/img/banner/bnr_el_description-exam.png)