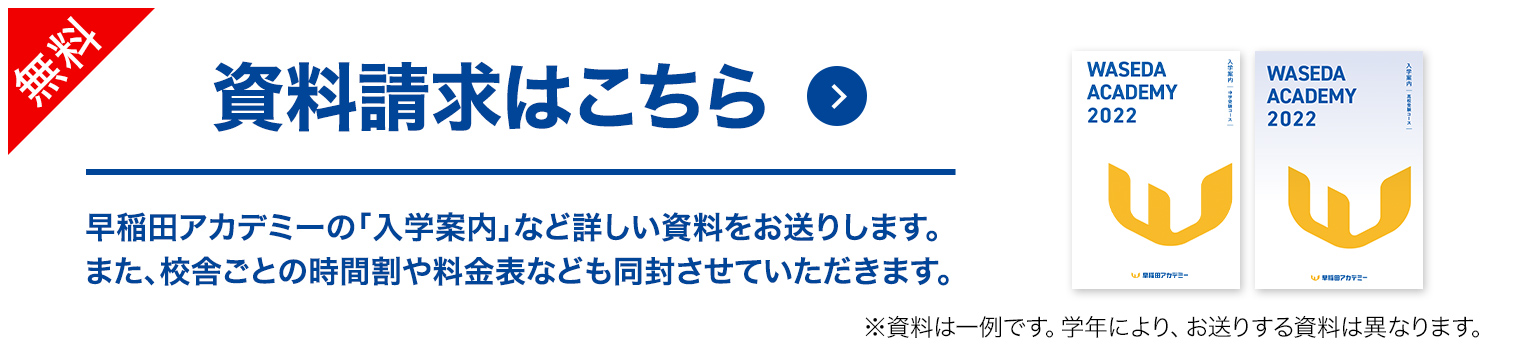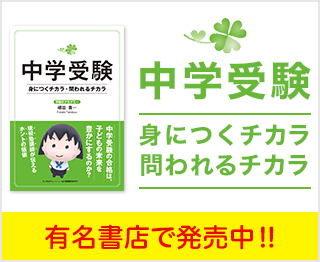『「選択」と「判断」』
2025.11.26
毎日の生活のなかで、人は「選択」と「判断」をし続けながら生きているといわれます。朝食に何を食べるか、今日は何を着ていくか、駅までは歩くか、バスに乗るか……。皆様もそんな「選択」や「判断」をしながら、日々過ごしていらっしゃるのではないでしょうか。
そんな日常における「判断」について考えてみます。朝着ていく服装をどんなふうに選んでいるか、という誰しもが経験したことのある事例について取り上げてみましょう。その判断をするためのポイントは大きく二つあるように思います。一つ目のポイントは、「どのような服を持っているか」という点です。持っている服の数や種類によって、「選択肢」の数が決まってきます。「選択肢」の数が少なければ「判断」は楽になりますが、この事例で考えると、それは少し寂しいことでしょう。
もう一つのポイントは、服以外の条件です。当日の天気や気温なども大きなファクターになるでしょう。その日にどのような場所に行くのか、どのような人に会うのかなども、「判断」の大きな要素になるはずです。
「判断」をするときに、自分では決めかねて誰かにアドバイスを求めたくなることもあります。最近のテレビの天気予報は、天気や気温の予測を伝えるだけではなく、服装のアドバイスをしてくれることも多いようです。「夜は北風が冷たくなりますので、厚手の上着でお出掛けください」などといった表現をよく耳にします。ただ、そのアドバイス通りにするかどうかも、それぞれの「判断」のはずです。余談ですが、私はネクタイの色を朝のテレビの「星占い」に頼ることがあります。自分の星座が最下位だったときに、一度締めたネクタイを外して、ラッキーカラーに変えたこともありました。
服装を選ぶときには、「持っている服の数が少ないのは寂しい」と書かせていただきましたが、より重要な「判断」をするときには、「選択肢」の数が少ないと困ってしまうことになります。社会に出てからは、「判断」する前にどれだけの「選択肢」を用意できるかが、とても大切になってくるはずです。問題が生じたときにいくつの解決策を思い浮かべられるか、という点が「正しい判断」につながる最初のポイントだと考えています。そして、「選択肢の数を増やす」ために必要なのは、知識と経験と思考力です。小学生から大学生までの学習には、知識の量を増やし、たくさんの思考経験を積み重ねることで、将来の「選択肢」を増やすことにもつながっているのです。
さて、その「選択肢」と「判断」を中学受験へ向けた学習の話で考えてみます。算数の問題を解くときの「選択肢」と「判断」を例にしてみましょう。入試問題レベルの算数の問題の解き方は一つ(一通り)ではありません。いろいろな切り口から考えることができますし、正解にたどり着くために複数のアプローチや手法が考えられる問題も多くあります。「速さ」の問題を例にすれば、「状況図」を使う方法や「ダイヤグラム」を使う方法がありますし、「周期算的」に考えてもよければ、「図形」の考え方を応用できる場合もあります。それらの方法から、どの解法を選択すれば確実に正解に行き着くのか、さらにより効果的かつ効率的に解くことができるのかを、「判断」して「選択」することが必要になってくるわけです。
言い換えれば、複数の解き方から、一番よい方法を判断し選択するというのが、算数の入試問題を解くためには必要なのですが、その方法をなるべくたくさん思いつくように学習を進めておくことが大切になります。そのために必要なのは、「考えて解く」という点を大切にした学習です。小3から小4の一学期くらいまでの学習単元は、「解き方」をメインに扱っています。授業で教わった「解き方」を覚えて、それをそのまま当てはめれば解ける問題がテキストでも並んでいます。ただ、問題の難度が上がってくると、その「解き方」を当てはめる手前の「考える」という過程が必要になってきます。そこを大切にしてほしいのです。
算数を苦手にしているお子様の場合、この「考え方」のところまで、覚えてしまおうとする場合があります。算数という科目を「考えて解く」のではなく、「知っていることを当てはめて解く」というように誤解をしてしまっているのです。もちろん、「○○算の解き方」という基本部分は「覚えて身に付けておく」ことから始まります。その数が多ければ、解くために使える「選択肢」の数が増えていくわけです。
中学受験の問題には正解があります。しかし、将来社会に出てから直面する問題には、「正解がない」といわれます。私自身も確かにその通りだと思います。社会人になってからも、解決策がマニュアルなどで提示されている問題は簡単です。しかし、社会人として悩む問題は「誰も正解を教えてくれない」問題であり、自分で考え、切り拓くことが必要なものなのではないでしょうか。そのために、小学生のときから学んでいるのだと、私は考えています。
与えられた問題に対して、多くの選択肢を思いつくための「知識と経験」、選択肢のなかから「最適解」を見つけていくための「判断力」、判断するための方法として「広い視野で考えること」「一つひとつの選択肢を比べて考えること」などなど。中学受験へ向けた学習は、志望校の入試問題で合格点をとるためだけではなく、将来にもつながる力を養うことにもつながっているのだと、私は考えています。
- 2025.11.26 『「選択」と「判断」』
- 2025.11.21 『科目による成績差』
- 2025.11.19 『こうなりたいリスト』
- 2025.11.14 『入試を成長機会と考える』
- 2025.11.12 『算数に必要な読解力』
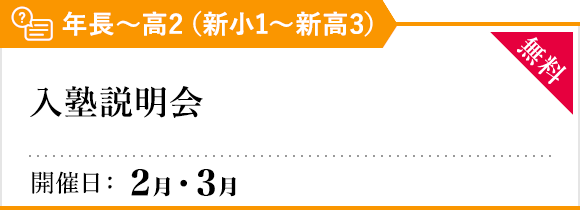


![トップレベル模試 [第1回]](/assets/img/banner/bnr_el_description-exam.png)