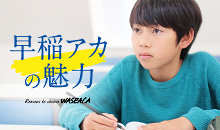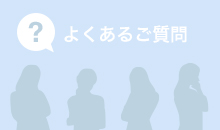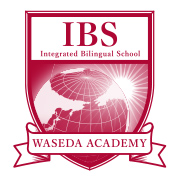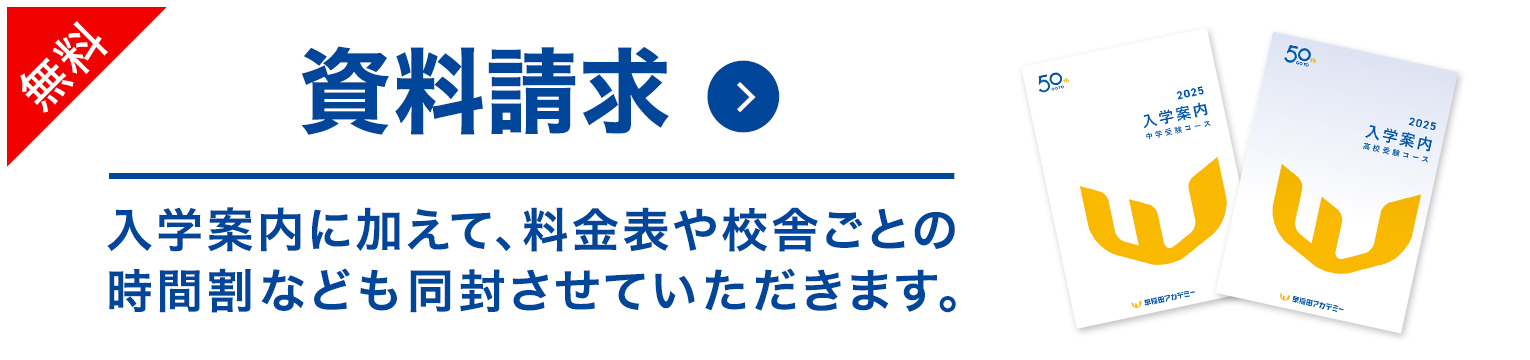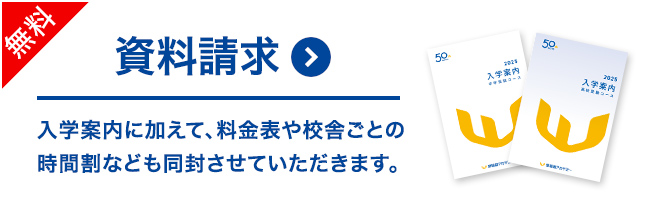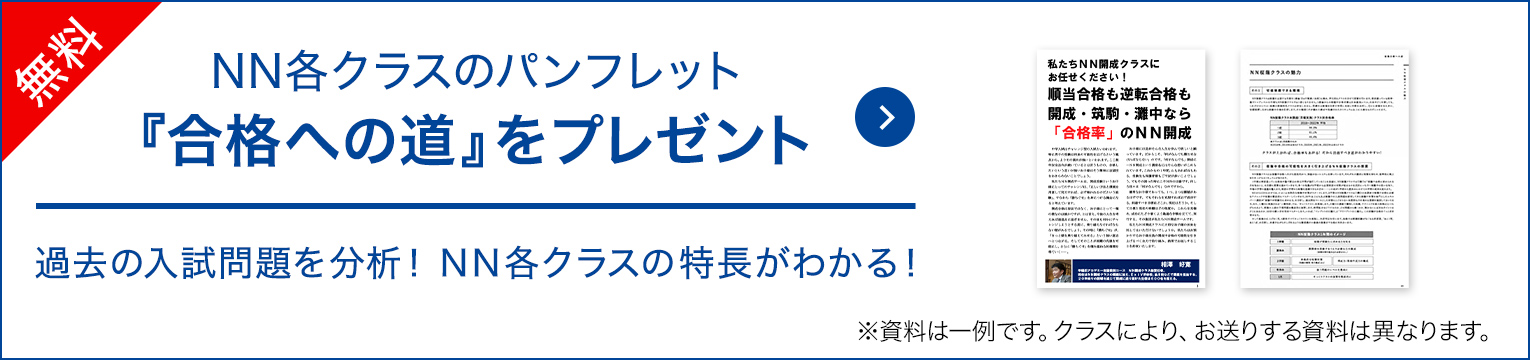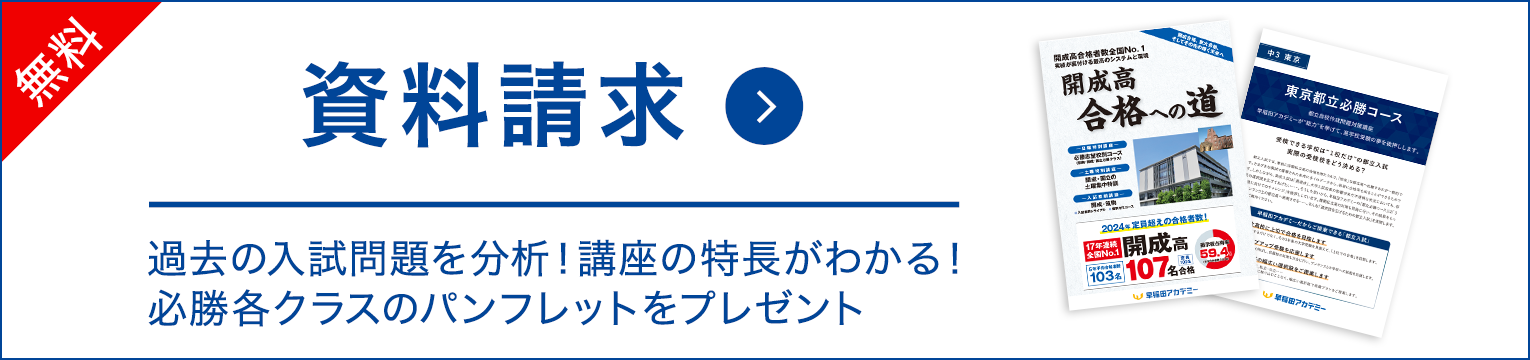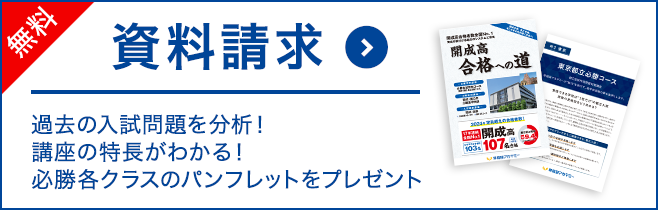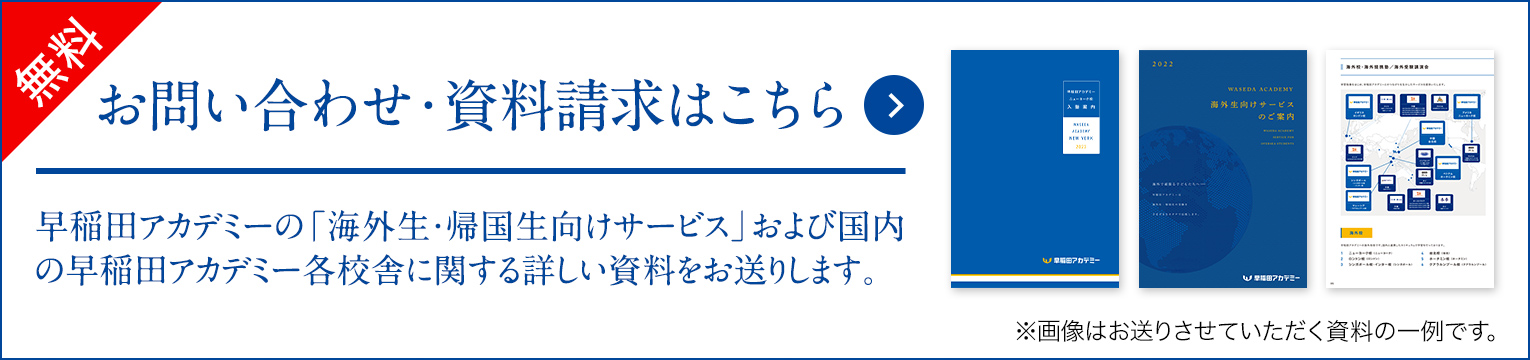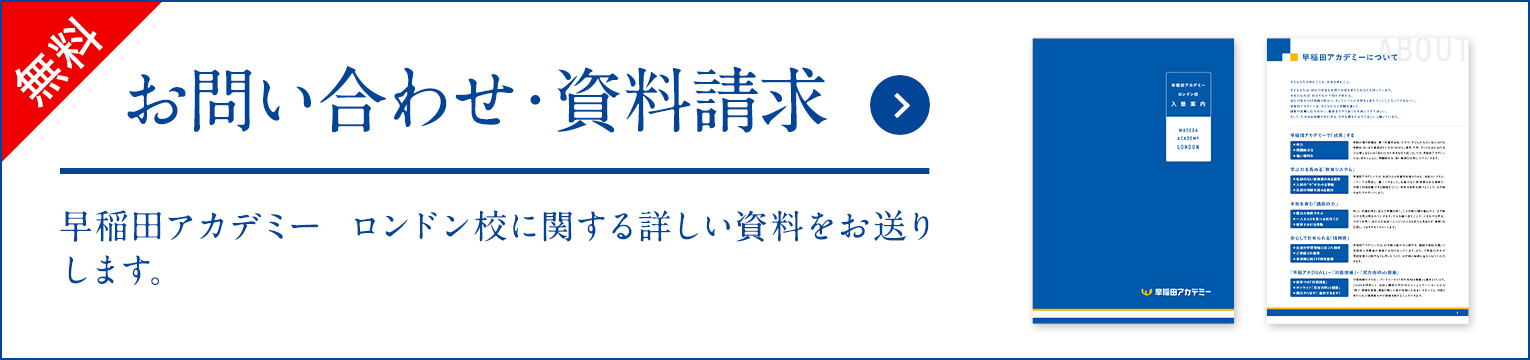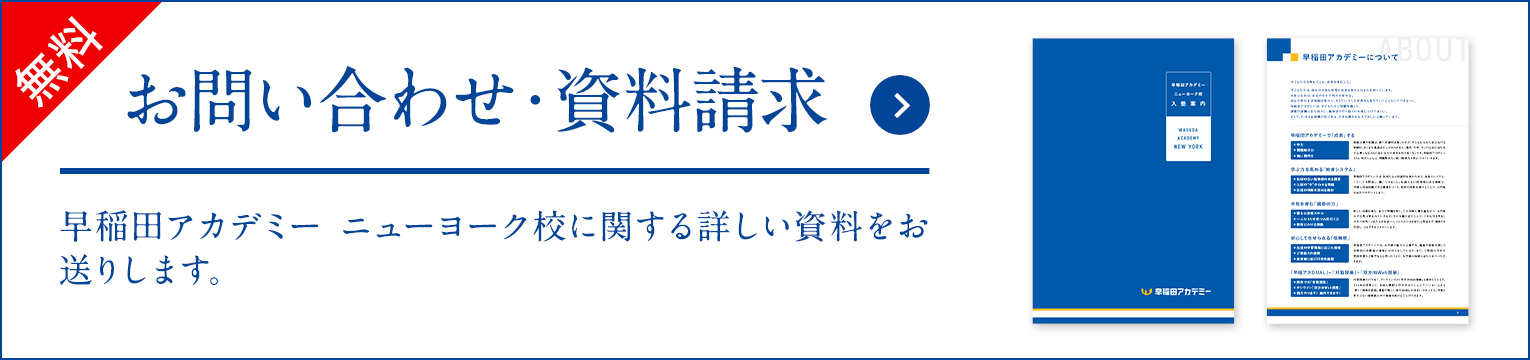小学5年生対象 Sコース学習内容
国語
| 第1回 | 物語・小説(1)/心情① 単語の学習① 品詞分類表・名詞/和語① |
|---|---|
| 第2回 | 物語・小説(2)/心情② 単語の学習② 動詞/慣用句① |
| 第3回 | 説明文・論説文(1)/話題 単語の学習③ 形容詞・形容動詞/三字の熟語 |
| 第4回 | 説明文・論説文(2)/形式段落 単語の学習④ 副詞・連体詞・接続詞・感動詞/四字の熟語 |
| 第5回 | 総合 |
| 第6回 | 物語・小説(3)/心情変化① 単語の学習⑤ 助動詞1/和語② |
| 第7回 | 物語・小説(4)/心情変化② 単語の学習⑥ 助動詞2/慣用句② |
| 第8回 | 説明文・論説文(3)/意味段落① 単語の学習⑦ 助詞1/同音異字・同音異義語 |
| 第9回 | 説明文・論説文(4)/意味段落② 単語の学習⑧ 助詞2/同訓異字 |
| 第10回 | 総合 |
| 第11回 | 随筆文(1)/経験と感想① 文節と文節の関係① 主語・述語・修飾語/和語③ |
| 第12回 | 随筆文(2)/経験と感想② 文節と文節の関係② 分けて〈関係〉を考える/慣用句③ |
| 第13回 | 説明文・論説文(5)/要旨① 文と文の関係① 接続関係1/類義語 |
| 第14回 | 説明文・論説文(6)/要旨② 文と文の関係② 接続関係2/対義語① |
| 第15回 | 総合 |
| 第16回 | 随筆文(3)/意見と理由① 文と文の関係③ 因果関係/外来語 |
| 第17回 | 随筆文(4)/意見と理由② 文と文の関係④ 具体と抽象/ことわざ |
| 第18回 | 物語・小説(5)/主題① 敬語①/対義語② |
| 第19回 | 物語・小説(6)/主題② 敬語②/四季の言葉(春・夏) |
| 第20回 | 総合 |
| 第1回 | 物語・小説(7)/心情変化③ 表現技法①/和語① |
|---|---|
| 第2回 | 説明文・論説文(7)/細部分析 表現技法②/慣用句① |
| 第3回 | 物語・小説(8)/性格と人物像 表現技法③/三字の熟語 |
| 第4回 | 詩/詩を読み解く 手紙文の約束事/四字の熟語 |
| 第5回 | 総合 |
| 第6回 | 物語・小説(9)/表現を読む 単語の学習① 助動詞/和語② |
| 第7回 | 説明文・論説文(8)/データや情報を読む 単語の学習② 助詞/慣用句② |
| 第8回 | 短歌/短歌を読み解く 文語的表現①/同音異字・同音異義語 |
| 第9回 | 俳句/俳句を読み解く 文語的表現②/同訓異字 |
| 第10回 | 総合 |
| 第11回 | 随筆文(5)/経験と感想③ 文節と文節の関係① 主語・述語・修飾語/外来語 |
| 第12回 | 随筆文(6)/意見と理由③ 文節と文節の関係② 分けて〈関係〉を考える/ことわざ |
| 第13回 | 物語・小説(10)/主題 文と文の関係① 接続関係1/類義語 |
| 第14回 | 説明文・論説文(9)/主張と根拠 文と文の関係② 接続関係2/対義語 |
| 第15回 | 総合 |
| 第16回 | 物語・小説(11)/物語・小説の読解総復習 文と文の関係③ 因果関係/故事成語 |
| 第17回 | 説明文・論説文(10)/説明文・論説文の読解総復習 文と文の関係④ 抽象と具体/四季の言葉(秋・冬) |
| 第18回 | 随筆文(7)/随筆文の読解総復習 文と文の関係⑤ 換言と対比/暦の知識 |
| 第19回 | 総合 |
| 第1回 | 物語・小説(1)/心情① 単語の学習① 品詞分類表・名詞/和語① |
|---|---|
| 第2回 | 物語・小説(2)/心情② 単語の学習② 動詞/慣用句① |
| 第3回 | 説明文・論説文(1)/話題 単語の学習③ 形容詞・形容動詞/三字の熟語 |
| 第4回 | 説明文・論説文(2)/形式段落 単語の学習④ 副詞・連体詞・接続詞・感動詞/四字の熟語 |
| 第5回 | 総合 |
| 第6回 | 物語・小説(3)/心情変化① 単語の学習⑤ 助動詞1/和語② |
| 第7回 | 物語・小説(4)/心情変化② 単語の学習⑥ 助動詞2/慣用句② |
| 第8回 | 説明文・論説文(3)/意味段落① 単語の学習⑦ 助詞1/同音異字・同音異義語 |
| 第9回 | 説明文・論説文(4)/意味段落② 単語の学習⑧ 助詞2/同訓異字 |
| 第10回 | 総合 |
| 第11回 | 随筆文(1)/経験と感想① 文節と文節の関係① 主語・述語・修飾語/和語③ |
| 第12回 | 随筆文(2)/経験と感想② 文節と文節の関係② 分けて〈関係〉を考える/慣用句③ |
| 第13回 | 説明文・論説文(5)/要旨① 文と文の関係① 接続関係1/類義語 |
| 第14回 | 説明文・論説文(6)/要旨② 文と文の関係② 接続関係2/対義語① |
| 第15回 | 総合 |
| 第16回 | 随筆文(3)/意見と理由① 文と文の関係③ 因果関係/外来語 |
| 第17回 | 随筆文(4)/意見と理由② 文と文の関係④ 具体と抽象/ことわざ |
| 第18回 | 物語・小説(5)/主題① 敬語①/対義語② |
| 第19回 | 物語・小説(6)/主題② 敬語②/四季の言葉(春・夏) |
| 第20回 | 総合 |
| 第1回 | 物語・小説(7)/心情変化③ 表現技法①/和語① |
|---|---|
| 第2回 | 説明文・論説文(7)/細部分析 表現技法②/慣用句① |
| 第3回 | 物語・小説(8)/性格と人物像 表現技法③/三字の熟語 |
| 第4回 | 詩/詩を読み解く 手紙文の約束事/四字の熟語 |
| 第5回 | 総合 |
| 第6回 | 物語・小説(9)/表現を読む 単語の学習① 助動詞/和語② |
| 第7回 | 説明文・論説文(8)/データや情報を読む 単語の学習② 助詞/慣用句② |
| 第8回 | 短歌/短歌を読み解く 文語的表現①/同音異字・同音異義語 |
| 第9回 | 俳句/俳句を読み解く 文語的表現②/同訓異字 |
| 第10回 | 総合 |
| 第11回 | 随筆文(5)/経験と感想③ 文節と文節の関係① 主語・述語・修飾語/外来語 |
| 第12回 | 随筆文(6)/意見と理由③ 文節と文節の関係② 分けて〈関係〉を考える/ことわざ |
| 第13回 | 物語・小説(10)/主題 文と文の関係① 接続関係1/類義語 |
| 第14回 | 説明文・論説文(9)/主張と根拠 文と文の関係② 接続関係2/対義語 |
| 第15回 | 総合 |
| 第16回 | 物語・小説(11)/物語・小説の読解総復習 文と文の関係③ 因果関係/故事成語 |
| 第17回 | 説明文・論説文(10)/説明文・論説文の読解総復習 文と文の関係④ 抽象と具体/四季の言葉(秋・冬) |
| 第18回 | 随筆文(7)/随筆文の読解総復習 文と文の関係⑤ 換言と対比/暦の知識 |
| 第19回 | 総合 |
- こちらのカリキュラムは予定です。変更になる場合がございます。
算数
| 第1回 | 倍数と約数の利用 |
|---|---|
| 第2回 | いろいろな図形の面積 |
| 第3回 | 割合の利用 |
| 第4回 | いろいろな差集め算 |
| 第5回 | 総合 |
| 第6回 | 濃さ |
| 第7回 | 売買損益 |
| 第8回 | 多角形の回転・転がり移動 |
| 第9回 | 円の回転・転がり移動 |
| 第10回 | 総合 |
| 第11回 | 場合の数-ならべ方- |
| 第12回 | 場合の数-組み合わせ方- |
| 第13回 | 速さとグラフ |
| 第14回 | 水量の変化 |
| 第15回 | 総合 |
| 第16回 | 旅人算とグラフ |
| 第17回 | いろいろな旅人算 |
| 第18回 | 数列と数表 |
| 第19回 | 図形上の点の移動 |
| 第20回 | 総合 |
| 第1回 | 比の利用 |
|---|---|
| 第2回 | 平面図形と比 ―相似の利用― |
| 第3回 | 平面図形と比 ―辺の比と面積比― |
| 第4回 | つるかめ算の応用と年令算 |
| 第5回 | 総合 |
| 第6回 | 速さと比 |
| 第7回 | 旅人算と比 |
| 第8回 | 平面図形と比 ―まとめと応用― |
| 第9回 | 図形の移動 |
| 第10回 | 総合 |
| 第11回 | 仕事に関する問題 |
| 第12回 | 水深の変化と比 |
| 第13回 | 整数の分解と構成 |
| 第14回 | 立方体・直方体の切断 |
| 第15回 | 総合 |
| 第16回 | 濃さと比 |
| 第17回 | いろいろな立体の求積 |
| 第18回 | いろいろな速さの問題 |
| 第19回 | 総合 |
| 第1回 | 倍数と約数の利用 |
|---|---|
| 第2回 | いろいろな図形の面積 |
| 第3回 | 割合の利用 |
| 第4回 | いろいろな差集め算 |
| 第5回 | 総合 |
| 第6回 | 濃さ |
| 第7回 | 売買損益 |
| 第8回 | 多角形の回転・転がり移動 |
| 第9回 | 円の回転・転がり移動 |
| 第10回 | 総合 |
| 第11回 | 場合の数-ならべ方- |
| 第12回 | 場合の数-組み合わせ方- |
| 第13回 | 速さとグラフ |
| 第14回 | 水量の変化 |
| 第15回 | 総合 |
| 第16回 | 旅人算とグラフ |
| 第17回 | いろいろな旅人算 |
| 第18回 | 数列と数表 |
| 第19回 | 図形上の点の移動 |
| 第20回 | 総合 |
| 第1回 | 比の利用 |
|---|---|
| 第2回 | 平面図形と比 ―相似の利用― |
| 第3回 | 平面図形と比 ―辺の比と面積比― |
| 第4回 | つるかめ算の応用と年令算 |
| 第5回 | 総合 |
| 第6回 | 速さと比 |
| 第7回 | 旅人算と比 |
| 第8回 | 平面図形と比 ―まとめと応用― |
| 第9回 | 図形の移動 |
| 第10回 | 総合 |
| 第11回 | 仕事に関する問題 |
| 第12回 | 水深の変化と比 |
| 第13回 | 整数の分解と構成 |
| 第14回 | 立方体・直方体の切断 |
| 第15回 | 総合 |
| 第16回 | 濃さと比 |
| 第17回 | いろいろな立体の求積 |
| 第18回 | いろいろな速さの問題 |
| 第19回 | 総合 |
- こちらのカリキュラムは予定です。変更になる場合がございます。
社会
| 第1回 | 魚はどこから? ~日本の水産業~ |
|---|---|
| 第2回 | くらしに役立つ資源 ~地下資源と電力~ |
| 第3回 | いろいろな工場 ~日本の工業(1)~ |
| 第4回 | うつりゆく工業のすがた ~日本の工業(2)~ |
| 第5回 | 総合 |
| 第6回 | 公害と環境問題 ~日本の工業(3)~ |
| 第7回 | 結びつく人と物と情報 |
| 第8回 | 日本と世界の結びつき |
| 第9回 | 日本のすがた |
| 第10回 | 総合 |
| 第11回 | 九州地方 |
| 第12回 | 中国・四国地方 |
| 第13回 | 近畿地方 |
| 第14回 | 中部地方 |
| 第15回 | 総合 |
| 第16回 | 関東地方 |
| 第17回 | 東北・北海道地方 |
| 第18回 | 日本のおもな都市・地形図の読み方 |
| 第19回 | 統計資料の読み方 |
| 第20回 | 総合 |
| 第1回 | 旧石器時代・縄文時代・弥生時代 |
|---|---|
| 第2回 | 古墳時代・飛鳥時代 |
| 第3回 | 奈良時代 |
| 第4回 | 平安時代 |
| 第5回 | 総合 |
| 第6回 | 鎌倉時代 |
| 第7回 | 室町時代 |
| 第8回 | 安土・桃山時代 |
| 第9回 | 江戸時代(1) |
| 第10回 | 総合 |
| 第11回 | 江戸時代(2) |
| 第12回 | 江戸時代(3) |
| 第13回 | 江戸時代(4) |
| 第14回 | 明治時代(1) |
| 第15回 | 総合 |
| 第16回 | 明治時代(2) |
| 第17回 | 大正時代 |
| 第18回 | 昭和時代 |
| 第19回 | 総合 |
| 第1回 | 魚はどこから? ~日本の水産業~ |
|---|---|
| 第2回 | くらしに役立つ資源 ~地下資源と電力~ |
| 第3回 | いろいろな工場 ~日本の工業(1)~ |
| 第4回 | うつりゆく工業のすがた ~日本の工業(2)~ |
| 第5回 | 総合 |
| 第6回 | 公害と環境問題 ~日本の工業(3)~ |
| 第7回 | 結びつく人と物と情報 |
| 第8回 | 日本と世界の結びつき |
| 第9回 | 日本のすがた |
| 第10回 | 総合 |
| 第11回 | 九州地方 |
| 第12回 | 中国・四国地方 |
| 第13回 | 近畿地方 |
| 第14回 | 中部地方 |
| 第15回 | 総合 |
| 第16回 | 関東地方 |
| 第17回 | 東北・北海道地方 |
| 第18回 | 日本のおもな都市・地形図の読み方 |
| 第19回 | 統計資料の読み方 |
| 第20回 | 総合 |
| 第1回 | 旧石器時代・縄文時代・弥生時代 |
|---|---|
| 第2回 | 古墳時代・飛鳥時代 |
| 第3回 | 奈良時代 |
| 第4回 | 平安時代 |
| 第5回 | 総合 |
| 第6回 | 鎌倉時代 |
| 第7回 | 室町時代 |
| 第8回 | 安土・桃山時代 |
| 第9回 | 江戸時代(1) |
| 第10回 | 総合 |
| 第11回 | 江戸時代(2) |
| 第12回 | 江戸時代(3) |
| 第13回 | 江戸時代(4) |
| 第14回 | 明治時代(1) |
| 第15回 | 総合 |
| 第16回 | 明治時代(2) |
| 第17回 | 大正時代 |
| 第18回 | 昭和時代 |
| 第19回 | 総合 |
- こちらのカリキュラムは予定です。変更になる場合がございます。
理科
| 第1回 | 季節と生物 |
|---|---|
| 第2回 | 物の温度による変化 |
| 第3回 | 物のあたたまり方 |
| 第4回 | 季節と星座 |
| 第5回 | 総合 |
| 第6回 | 気象の観測 |
| 第7回 | 天気の変化 |
| 第8回 | てこと輪軸 |
| 第9回 | 植物のつくり |
| 第10回 | 総合 |
| 第11回 | 植物の成長 |
| 第12回 | 水溶液の濃さ |
| 第13回 | 物の運動 |
| 第14回 | 太陽系の天体 |
| 第15回 | 総合 |
| 第16回 | 気体(1) |
| 第17回 | 気体(2) |
| 第18回 | 植物のはたらき |
| 第19回 | 地球 |
| 第20回 | 総合 |
| 第1回 | 生物のつながり |
|---|---|
| 第2回 | てこ・滑車・輪軸 |
| 第3回 | 水溶液の中和 |
| 第4回 | ヒトと動物の消化・吸収 |
| 第5回 | 総合 |
| 第6回 | ヒトと動物の呼吸・循環 |
| 第7回 | 物の燃焼 |
| 第8回 | ばね・浮力・圧力 |
| 第9回 | 流水と地層 |
| 第10回 | 総合 |
| 第11回 | 光と音 |
| 第12回 | 火山と地震 |
| 第13回 | 生命の誕生 |
| 第14回 | 電流と抵抗 |
| 第15回 | 総合 |
| 第16回 | 電流と磁界 |
| 第17回 | 太陽の動き |
| 第18回 | 太陽と地球 |
| 第19回 | 総合 |
| 第1回 | 季節と生物 |
|---|---|
| 第2回 | 物の温度による変化 |
| 第3回 | 物のあたたまり方 |
| 第4回 | 季節と星座 |
| 第5回 | 総合 |
| 第6回 | 気象の観測 |
| 第7回 | 天気の変化 |
| 第8回 | てこと輪軸 |
| 第9回 | 植物のつくり |
| 第10回 | 総合 |
| 第11回 | 植物の成長 |
| 第12回 | 水溶液の濃さ |
| 第13回 | 物の運動 |
| 第14回 | 太陽系の天体 |
| 第15回 | 総合 |
| 第16回 | 気体(1) |
| 第17回 | 気体(2) |
| 第18回 | 植物のはたらき |
| 第19回 | 地球 |
| 第20回 | 総合 |
| 第1回 | 生物のつながり |
|---|---|
| 第2回 | てこ・滑車・輪軸 |
| 第3回 | 水溶液の中和 |
| 第4回 | ヒトと動物の消化・吸収 |
| 第5回 | 総合 |
| 第6回 | ヒトと動物の呼吸・循環 |
| 第7回 | 物の燃焼 |
| 第8回 | ばね・浮力・圧力 |
| 第9回 | 流水と地層 |
| 第10回 | 総合 |
| 第11回 | 光と音 |
| 第12回 | 火山と地震 |
| 第13回 | 生命の誕生 |
| 第14回 | 電流と抵抗 |
| 第15回 | 総合 |
| 第16回 | 電流と磁界 |
| 第17回 | 太陽の動き |
| 第18回 | 太陽と地球 |
| 第19回 | 総合 |
- こちらのカリキュラムは予定です。変更になる場合がございます。
カリキュラムテスト
自分と同じ到達度のライバルと競い合う
隔週土曜日に、学力別に分かれたテストを実施します。学力を伸ばすためには「適切な評価」と「競争」が必要です。カリキュラムテストは学力別の問題が用意されているため、自分と同じ到達度のライバルと競い合うことができます。
イベント・模試・講習会情報
セミナー・イベント
無料
講座・講習会
講座・講習会
講座・講習会
講座・講習会
模試・テスト
無料
セミナー・イベント
無料
関連コンテンツ
中学受験に関する不安や疑問について、早稲田アカデミーがお答えします
早稲田アカデミーは生徒の「第一志望校合格」を全力で応援します
合格体験記 公開中!
基本コースに加え、学習目的に合わせたさまざまなコース・講座をご用意しています。
オプションコース・講座
小5から始める難関中対策
身に付く本物の英語力
「英書多読」を通じて育む「英語脳」
おすすめピックアップ
豊富なコースから最適なコースをお探しいただけます
中学・高校・大学入試の合格実績がご覧になれます
見れば見るほどよくわかる! 楽しく学べる学習ムービー!
早稲田アカデミーの教育に対する想いを乗せたムービーです