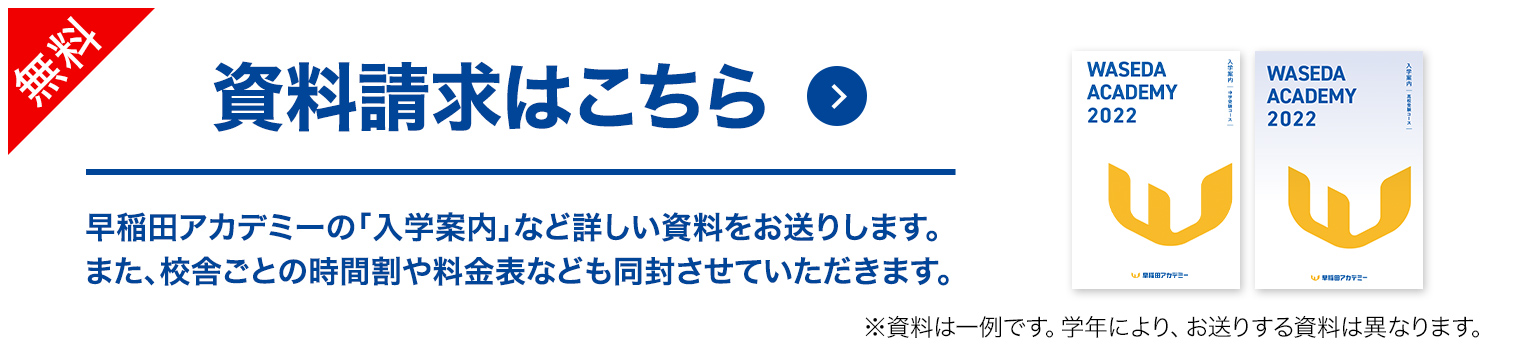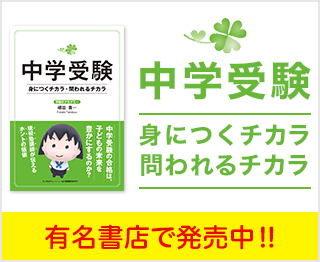『子どもの言語感覚~オノマトペから考える~』
2025.07.02
「オノマトペ」という言葉をご存じでしょうか。わかりやすく言えば、「擬音語(擬声語)」と「擬態語」の総称となります。この「オノマトペ」に関する問題は、小学生の国語でよく出題されます。先日実施された「全国統一小学生テスト」でも出題されていました。小学生の言語感覚レベルを確認するのに、オノマトペの問題は非常に有効といわれています。もちろん、その語を「知っているか・知らないか」でも問題は解けるのですが、知らない言葉でも「言葉の感覚」で考えることができるためです。少し珍しいオノマトペを例にあげてみます。
問 「こおろこおろ」という言葉はどんなときに使われる表現ですか。 ア.自転車がゆっくり走っているとき イ.貼ってあるシールをはがしているとき ウ.液体をゆっくりかきまぜているとき エ.鉛筆を指先でくるくる回しているとき
実はこの「こおろこおろ」という表現は、「日本最古のオノマトペ」といわれています。『古事記』の有名な「国生み」の場面で、イザナギとイザナミが、「天の沼矛(ぬほこ)」を混沌とした海に差し込んでかき回すときに使われているのです。ですから、答えはウということになります。
問 「どっどど どどうど どどうど どどう」という表現は、何の音や様子を表したものでしょう。 ア.蒸気機関車が走る音や様子 イ.大きな木が切り倒される音や様子 ウ.本棚から大きな本を取り出す音や様子 エ.強い風が吹く音や吹いている様子
こちらはご存じの方も多いでしょう。「オノマトペの名手」といわれることもある宮沢賢治の『風の又三郎』の冒頭に出てくる表現です。答えはエです。宮沢賢治の作品には、既成のものにとらわれない、自身の感性に沿ったオリジナルの表現が多く使われます。そこが面白く、小学生の子どもにも読ませたいところです。『どんぐりと山猫』に出てくる「まわりの山は、みんなたったいまできたばかりのようにうるうるもりあがって……」という表現などは、国語の授業でも取り上げてみたい擬態語です。
大人になると「頭が固くなる」といわれます。脳生理学的にどうなのかという点については、専門外なので私にはわかりませんが、私なりに考えていることはあります。
「雨の降る様子」を例にとって考えてみます。大人になってくると、さまざまな経験もしていて、知識も増えてきます。当然、「雨の降る様子」を表す言葉も多く蓄積されているはずです。そうなってくると、「今降っている雨」を表すのに適切な言葉を頭のなかで探すことになるのではないでしょうか。「ぽつぽつ」「ぱらぱら」「ざあざあ」「しとしと」「ぱしゃぱしゃ」などなど。しかし、子どもたちはそんなにたくさんの言葉を知りません。ですから、見た様子や音を自分で考えて表現するのだと思います。その「自分で考える」というところが「頭の柔らかさ」といわれ、「知っていることを使う」というのは「頭の固さ」となるように思うことがあります。
以前、授業の始まる前に、雨が降り始めた日がありました。ずっと校舎のなかにいた私は、ある生徒に「雨が降ってきたの?どんな感じ?」と尋ねました。すると彼女は「うーん……ポシャポシャ……っていう感じ!」と答えてくれました。「ポシャポシャ」というのは一般的な表現ではありません。でも、とてもイメージが伝わる表現でした。「ピシャピシャ」や「ピチャピチャ」よりも少し雨粒が大きくて、それが地面のアスファルトにあたって跳ね返る、そんな感覚でしょうか。調べてみたところ、「ぽしゃぽしゃ」という表現は、やはり宮沢賢治が使っていました。詩集『春と修羅』の一遍の冒頭に出てきていました。ご興味のある方は調べていただければと思います。
「てちてち歩く」という表現をご存じでしょうか。犬を散歩させているときに、その様子を見た小学校低学年の女の子が「てちてち歩いていて、かわいい!」と言ってくれました。フレンチブルドッグという足の短い犬種で、その犬が一生懸命歩いている姿を「てちてち」と表現したようです。「とことこ」というほど軽快でもなく、とは言っても「よたよた」ではなく……。「うまい表現だな」と思いました。その子のオリジナルの表現なのかと思ったのですが、「てちてち歩く」という表現は、最近使われ始めている表現のようです。オリジナルは「ハムスターをキャラクターにしたアニメ」のようです。そこから広まり、「よちよち」から少し進んだ子どもの歩き方なども「てちてち」と表現されることがあるようです。
言葉も進化していくのだなと思いました。
- 2025.07.02 『子どもの言語感覚~オノマトペから考える~』
- 2025.06.27 『米』
- 2025.06.25 『ベストパフォーマンスを発揮する』
- 2025.06.20 『ドーナツの思い出』
- 2025.06.18 『小数の学習』
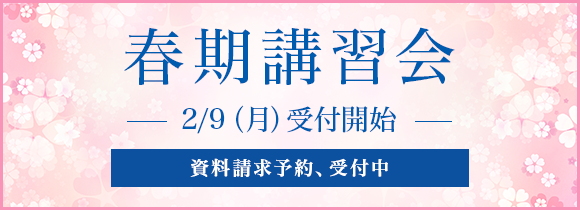
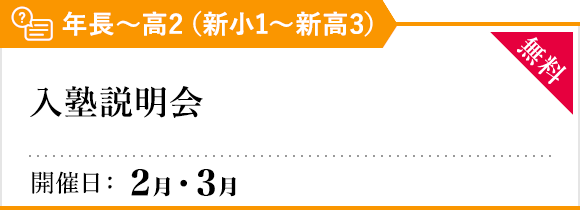


![トップレベル模試 [第1回]](/assets/img/banner/bnr_el_description-exam.png)