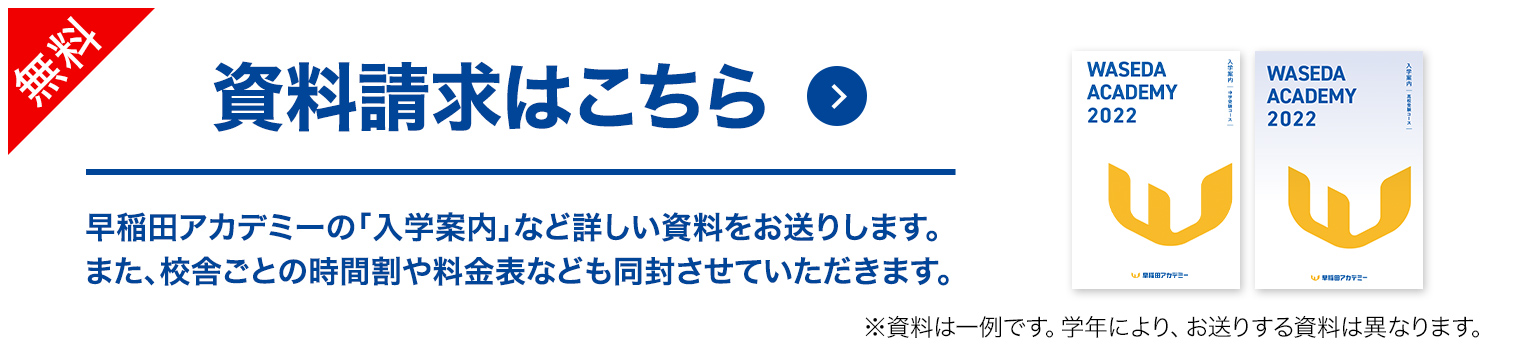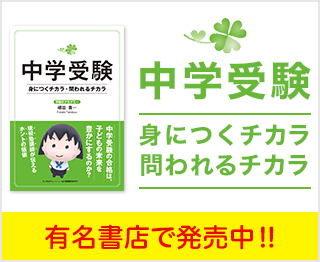『自分で考えることができる、丁寧に学習できる』
2025.07.30
「どのようなタイプの子どもが中学入試に向いていますか」という質問をいただくことがあります。特に雑誌の取材などで聞かれることが多いのですが、正直に言うと、「どんなタイプ・性格でも、中学入試に向かないお子様はいません」というのが、私の回答です。それぞれのタイプに合う中学校はありますし、どんな性格のお子様でも中学入試で成功するための学習の仕方はあるはずです。
ただ、そんなふうにお答えしても、「もう少し、何かありませんか?」と突っ込んで質問されることがあります。そんなときには、いくつかのタイプを例に挙げてお話ししています。そもそものお子様の性格というよりも、小学校低学年から中学年くらいにかけて、その方向性で伸ばしていくとよいという意味での『タイプ』です。「低学年から中学年で伸ばしていきたい力」とお考えいただいた方がよいかもしれません。
「中学入試で成功するタイプ」「中学入試に向けて伸ばしていきたい力」という観点から、今回は「二つの力」について、書かせていただきます。
一つ目は「自分で考える」という力です。 2020年度からスタートした小学校の新学習指導要領について文部科学省のホームページを見てみると、「自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え……」「主体的な学習」といった言葉が見つかります。現在求められているのは「主体的に、自ら学ぶ」という学習姿勢なのです。そして、中学入試だけではなく高校入試・大学入試も含めて、この点が問われているのだとお考えください。
小学生であれば、誰もが「依存心」を持っています。お父様やお母様に助けてもらいたいという気持ちを持っていない小学生はいないでしょう。しかし、勉強や学習という点においては、なるべく早くこの「依存心」から脱却して、「自分で考える」という方向に進めていくのがよいと考えています。
例えば、授業中の問題演習時間、少し難しい問題になると手を止めてボーっとしてしまっている生徒がいます。心のなかでは「先生、早く解説してくれないかなぁ」とつぶやいているように思えてしまいます。また、同じような問題について何回も繰り返し質問に来る生徒がいます。解説を聞くと笑顔になってくれるのですが、また同じ問題が自分では解けなくて質問に来てしまうのです。どちらの生徒も「自分で考える」ことが十分にできておらず、誰かに解説してもらうことで「解決したつもり」になり、安心してしまうタイプになってしまっているのです。このスタイルの学習では、大きな成績向上が望めないことはおわかりいただけると思います。
二つ目は、「丁寧に学習する」という力です。 「丁寧に」と聞くと、「字をきれいに書く」「筆算の位をきちんとそろえて計算する」といった力を想像されるかもしれません。しかし、ここでいう「丁寧な学習」は、「丁寧に考えることができる」という意味です。算数であれば、設問文を読んで条件を整理し、正解までの道筋を丁寧に考える、国語であれば、選択肢問題を「なんとなく」で選ばず、きちんと根拠を考え選択肢同士を比較して解く、記述問題ではいきなり解答を書き始めるのではなく内容を整理してから書く……というイメージです。
もちろん、低学年・中学年段階で、問題を解くときにそこまで「丁寧に」というのは要求できない部分もあります。ただ、「論理的に筋道を立てて考える」という姿勢の土台は、今のうちからつくっていけるとよいでしょう。
算数では図をきちんと書くところから、国語では段落や場面ごとに内容を把握しながら読むところから。そんな学習を進めていくのがよいと思います。
- 2025.07.30 『自分で考えることができる、丁寧に学習できる』
- 2025.07.25 『夏の刺激』
- 2025.07.23 『一生に一回の夏休み』
- 2025.07.16 『本との出会い』
- 2025.07.11 『暑熱順化と朝学習』
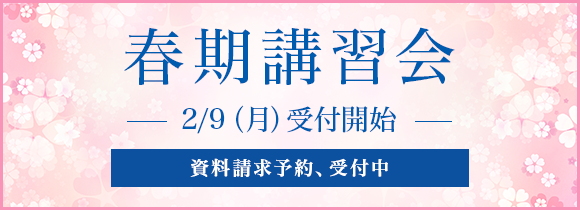
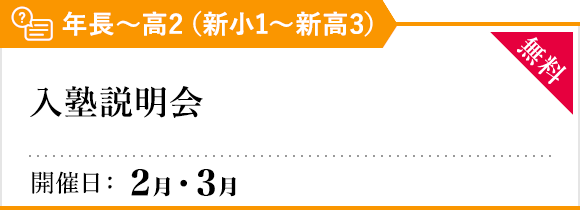


![トップレベル模試 [第1回]](/assets/img/banner/bnr_el_description-exam.png)